若者たちから絶大な支持を集めたATG

アート・シアター・ギルドは、所謂ミニシアターの先駆け的な組織で、映画配給のみではなく、映画製作にも関わっていました。アート・シアター・ギルド(ATG)は、全共闘世代の若者たちから絶大な支持を集め、一時は日本映画の潮流を牽引する存在でさえあったのです。 ATGは会員制で、年会費を払うと良質な映画を割安で鑑賞することができる点が、学生たちに支持されました。当時は新宿が若者文化の中心だったので、ATGの上映館、新宿文化は話題の映画がかかると満員になったそうです。 惜しまれつつ1992年に活動停止してしまった、伝説のATGとはどんな組織だったのか? 年代を追ってご紹介します。
「日本アート・シアター・ギルド」の概要
アート・シアター・ギルドとは正式名称が日本アート・シアター・ギルドで、略称ATGという、1960年代から1980年代に日本に存在した映画会社です。 非商業的な芸術系映画を製作・配給し、後の邦画界に大きな影響を与える人材を育てました。また、作品が公開される度に『アートシアター』という機関誌が発行され、映画の全シナリオと評論を収録。 また、映画史的に重要な外国作品の上映も行うなどの活動もしていましたし、さらには映画界のみに留まらず、演劇界、テレビ業界の人材にも映画を撮らせていたのです。 まさに映画界に新風を吹き込んだ会社と言えます。
ATG誕生の歴史的背景と経緯

ATG設立の歴史的背景としては、1960年代から1970年代初頭の学生運動の影響が強いと思われます。若者たちの関心はシリアスなアート系映画やアングラ演劇などに向かっていたのです。 加えて、1950年代に芸術映画や前衛的な実験映画を上映する映画館を作る、アートシアター運動がアメリカで起こっていました。 また、1960年代はアンジェイ・ワイダなどのポーランド派、ゴダールなどのヌーヴェルヴァーグの影響もあって、芸術映画の需要は高まっていたのです。 そのような背景のもと、東和映画副社長の川喜多かしこと東宝副社長の森岩雄が協力して、アートシアター設立に乗り出しました。三和興行の井関種雄を社長に据えて、フィルム・ライブラリーの充実、資金集め、上映館の確保などが順次行われます。
主に外国映画を配給していた第一期(1961〜1967)

1961年から1967年、所謂、第一期のATGの活動は、主に国内外のアート映画の配給で、映画制作は行っていませんでした。 ATGの第一回配給作品はイエジー・カワレロウィッチの『尼僧ヨアンナ』(1961)。その後、コクトー、勅使河原宏、デ・シーカ、ベルイマン、ヌーヴェルヴァーグの監督たちの作品を次々に紹介したのです。 数年後、三島由紀夫が原作・監督・脚本・製作・主演をこなした短編映画、『憂国』(1966)のヒット、今村昌平監督がドキュメンタリー映画、『人間蒸発』(1967)の企画をATGに持ち込んだことにより、映画制作に関わりようになりました。
低予算映画を製作していた第二期(1967〜1979)
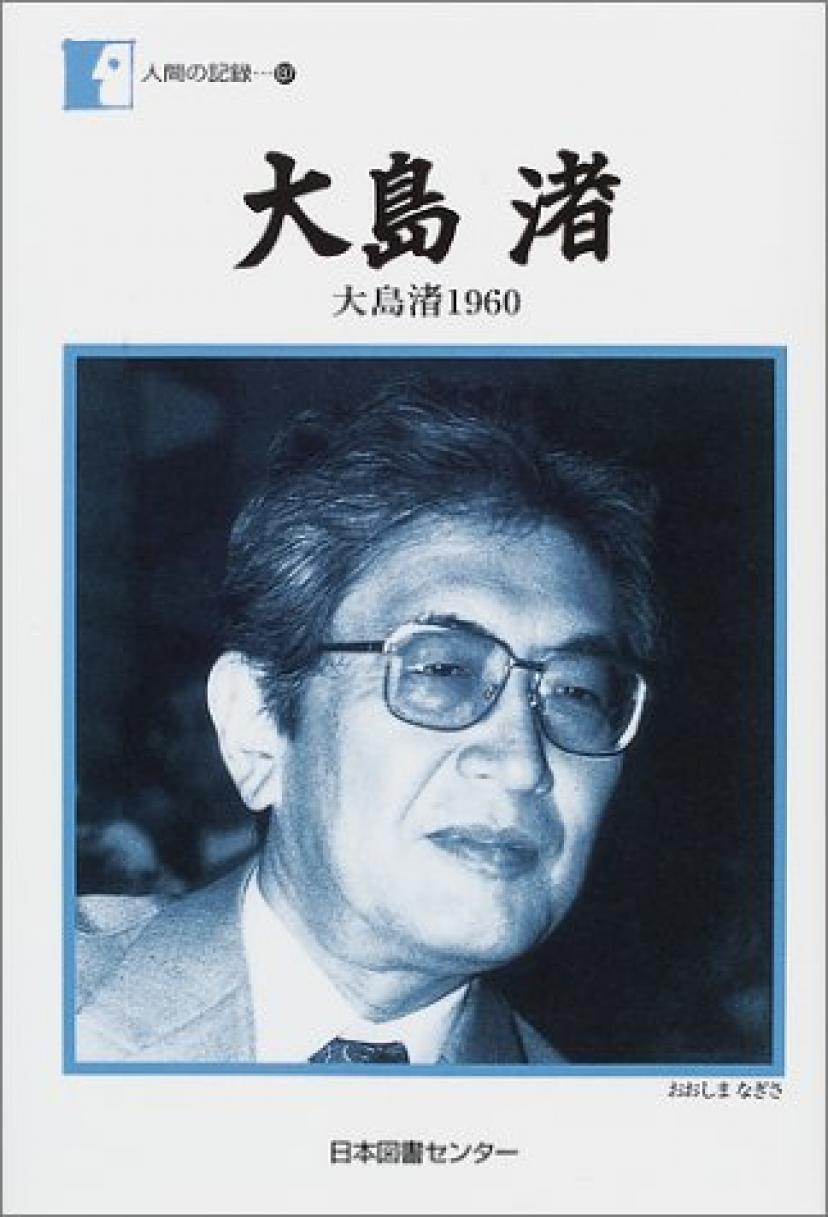
1967年、一般家庭にテレビが普及し、大手映画会社はこれに対抗するために娯楽映画を量産するようになりました。このため、大島渚や篠田正浩、吉田喜重のように、大手映画会社を離れる監督たちが現れます。 ATGはこうした監督たちが立ち上げた独立プロを支援し、低予算映画を製作するようになるのです。岡本喜八の『肉弾』(1968)、若松孝二の『天使の恍惚』(1972)などは、そうした状況下で作り出されました。 また、実相寺昭雄、田原総一朗などテレビ界、寺山修司、唐十郎など演劇界の人材が映画を撮ることができる環境も、ATGが作ったのです。
若手を起用した第三期と衰退(1979〜1992)
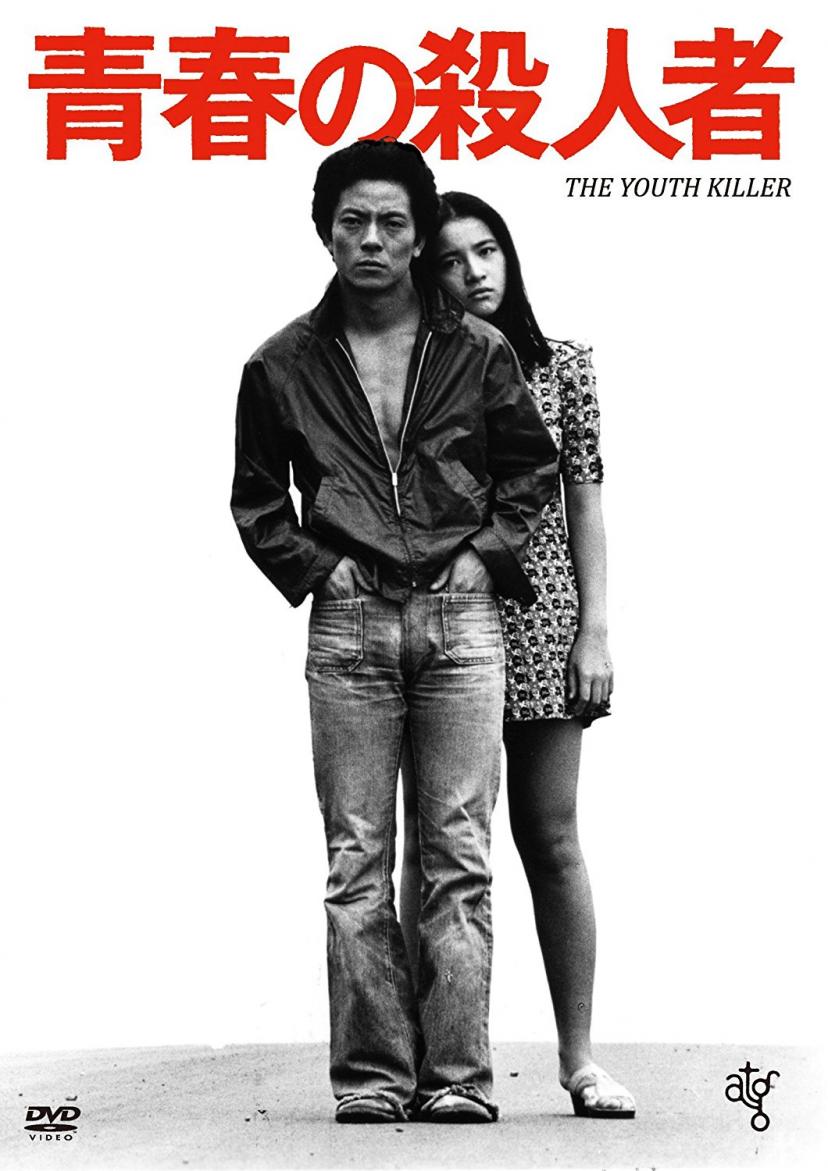
ATGが製作を支援した芸術映画の中には興行的に失敗するものもあり、経営は徐々に困難になっていきます。1979年に井関種雄社長が辞職し、佐々木史朗が社長に就任。 佐々木社長率いるATGは大物よりも、大森一樹、森田芳光などの若手監督や、長谷川和彦、井筒和幸などのポルノ映画出身の監督を積極的に起用するようになりました。 森田芳光の『家族ゲーム』(1983)のヒットはそのような経緯で生まれたものです。重要な映画人を育成したものの、ATG自体は徐々に弱体化していき、1992年、新藤兼人監督『濹東綺譚』を最後に活動を停止します。
ATGをめぐるトリビア
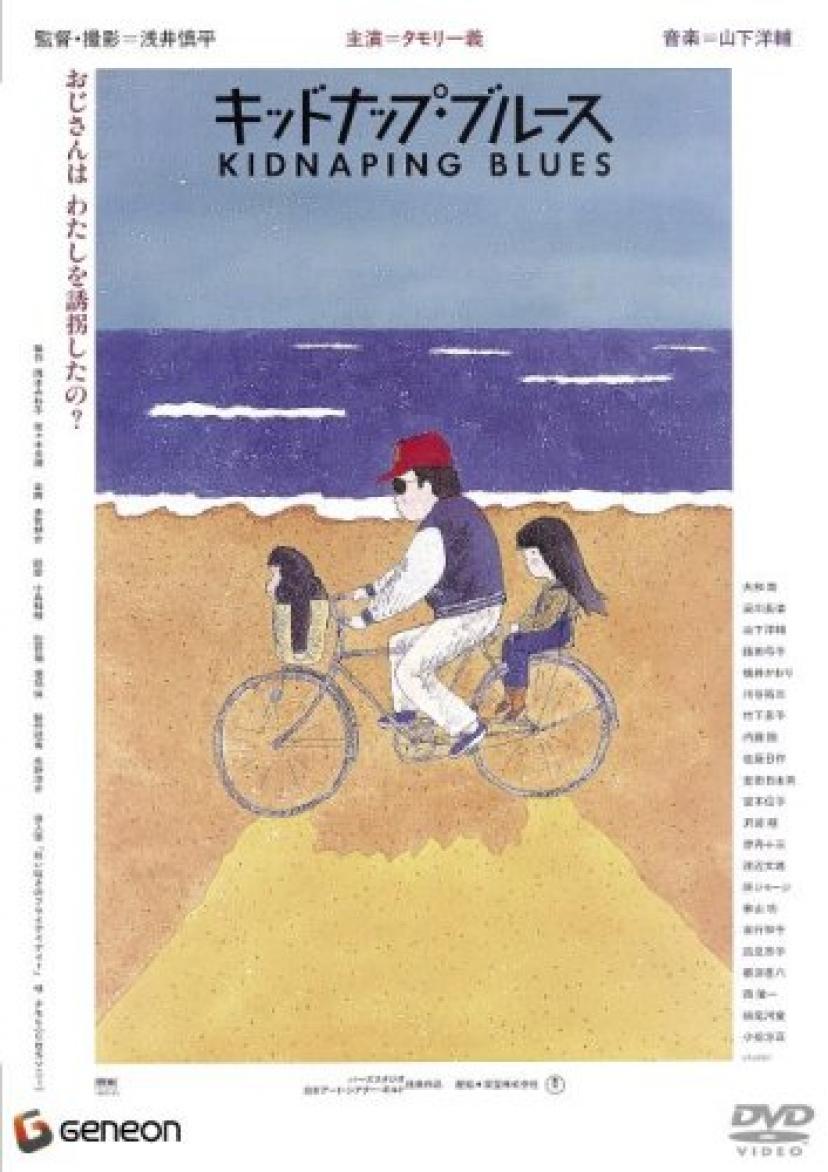
ATGの映画製作は、独立プロと製作費を折半し、「一千万円映画」と呼ばれる低予算でした。1000万円という予算は1960年代から1970年代当時、一般映画予算の数分の一であったため、製作には非常な困難が伴ったようです。 ATGのロゴマークのデザイン、機関誌『アートシアター』のタイトル・表紙デザインは伊丹十三が担当し、伊丹十三が映画監督デビューを果たした作品、『お葬式』(1984)を配給したのはATGです。 ATGが製作に関わった映画の中には、写真家の浅井慎平が監督し、タモリが主演した『キッドナップ・ブルース』(1982)という珍品もあります。
映画革新の受け皿としてのATG
いかがでしたか? 1960年代から1970年代の自由闊達な雰囲気とともに記憶されるべき、映画会社と言えます。もともとの設立の趣旨が、芸術映画および前衛映画の紹介であるがゆえに、いずれも先鋭的な感覚をもつ映画人が集まっていたようです。 フランスのヌーヴェルヴァーグ、イタリアのネオレアリズモ、アメリカのニューシネマなど、時代の変わり目には若者文化の中から革新運動が出現します。ATGはそうした運動の格好の受け皿になっていたのかもしれません。 次世代のATG的な存在を期待したいところです。
![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)






















