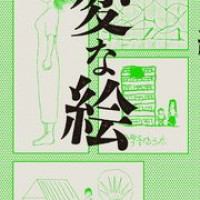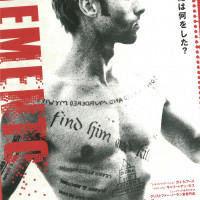【三宅唱監督に聞く】『旅と日々』制作秘話!原作にはない“包帯”の秘密と演出の意図とは?
2025年11月7日公開、三宅唱監督の最新作『旅と日々』。つげ義春の世界観に深く触れながらも、その世界をなぞるのではなく、三宅監督ならではの繊細なまなざしで“旅”と“生”が静かに、そして力強く描き出されています。 これまで過去の名作を観てきた中で、その素晴らしさや感動、驚きに心を動かされる一方で、「この作品をリアルタイムで体験できなかった」という小さな悔しさを覚えることもありました。 しかし『旅と日々』は、まさに“今”という時代に生まれた奇跡のような映画です。かつての名作を観たときのような深い充足と余韻を、2025年という現在において味わうことができる――そんな特別な一本。極上の映画体験を、ぜひ劇場でご堪能ください。 本作の公開を記念して、三宅唱監督にインタビューを実施。つげ作品を映画として昇華させるうえでの創作意識、シム・ウンギョンさん、河合優実さん、堤真一さんら俳優陣のキャスティング背景、そしてキャラクター造形に込めた思いなど――貴重な制作の裏側をじっくりと伺いました。 原作にはない、渚(河合優実)が指に包帯をしている映画ならではの設定の意図とは? 三宅監督が考える映画の本質とは? ※インタビュー取材の模様を撮影した動画コンテンツをYouTubeのciatr/1Screenチャンネルで公開中!
タップできる目次
- 映画『旅と日々』作品概要・あらすじ
- 【制作経緯】読む人、読む瞬間で受け止め方が変容するつげ義春作品の謎、魅力に迫りたい
- 【キャラ造形・キャスティング背景①】映画黄金期のスターのような光を放つシム・ウンギョンの魅力
- 【キャラ造形・キャスティング背景②】河合優実と積み上げた渚の「からっぽ」というキーワード
- 【キャラ造形・キャスティング背景③】扉を開けた瞬間に感じた髙田万作の夏男らしさ
- 【キャラ造形・キャスティング背景④】無言でも滲み出る堤真一の"べん造”としての佇まい
- 【撮影秘話】三宅監督が初めて決断・経験したまるごとリテイクしたシーンとは?
- 【撮影秘話】渚と夏男が海で泳ぐシーンは"迫力”が必要不可欠だった
- 【撮影のテーマ】コントロールできない事象をどう捉えるか?
- 【音へのこだわり】つげ義春作品特有の直感的な"怖さ”を音で表現
- 【オープニングの演出意図】セリフなしのOP5分、最初のセリフが「Ciao」であることのおかしみ
- 【劇中劇の構造】映画で何度も“驚く”という経験を生み出したかった
- 【三宅唱監督が考える“映画の本質”】日常の隙間に潜むものを発見する――その瞬間の“驚き”
- 映画『旅と日々』は2025年11月7日より公開中
映画『旅と日々』作品概要・あらすじ
| 公開日 | 2025年11月7日 |
|---|---|
| 上映時間 | 89分 |
| 監督・脚本 | 三宅唱 |
| 撮影 | 月永雄太 |
| 音楽 | Hi'Spec |
| キャスト | シム・ウンギョン , 河合優実 , 高田万作 , 堤真一 |
映画『旅と日々』は、つげ義春の短編漫画「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」を原作に、三宅唱監督が現代の感性で新たに再構築した作品です。 2020年にアングレーム国際漫画祭で特別栄誉賞を受け、“漫画界のゴダール”と称されたつげの世界を、50年以上の時を経てスクリーンに甦らせます。 本作は、世界で最も長い歴史を誇るロカルノ国際映画祭のインターナショナル・コンペティション部門にて最高賞である金豹賞&ヤング審査員賞特別賞をW受賞しました。三宅監督にとっては『Playback』(2012)以来、13年ぶりの同部門への出品であり、日本映画の金豹賞選出は18年振りの快挙。選考委員会からは「日本映画の最高峰」との賛辞を受けています。 物語の主人公は、創作に行き詰まった脚本家・李。旅の途中で出会う人々とのささやかな交流を通じて、彼女はほんのわずかに、しかし確かに前へと歩み出していきます。夏の海と冬の雪原――対照的な季節の風景の中で紡がれるのは、人と人とが触れ合い、心を通わせる瞬間の輝き。 主演のシム・ウンギョンをはじめ、堤真一、河合優実、髙田万作、佐野史郎ら実力派俳優陣が集い、静謐で温かなまなざしが観る者の心をやさしく包み込みます。人生の旅路に寄り添うように、静かに心を潤す――『旅と日々』は、現代に生きる私たちの“今”に深く響く、珠玉の映画です。
三宅唱監督プロフィール

| 生年月日 | 1984年7月18日 |
|---|---|
| 出身地 | 北海道 |
| 出身校 | 映画美学校フィクションコース初等科 一橋大学社会学部 |
| フィルモグラフィー | 『やくたたず』(2010年):監督 『Playback』(2012年):監督・脚本・編集 『THE COCKPIT』(2014年):監督・編集 『密使と番人』(2017年) :監督・脚本 『きみの鳥はうたえる』(2018年):監督・脚本・編集 『ワイルドツアー』(2019年) :監督・脚本 『ケイコ 目を澄ませて』(2022年): 監督・脚本 『夜明けのすべて』(2024年): 監督・脚本(和田清人との共同脚本) 『旅と日々』(2025年): 監督・脚本 |
三宅唱監督は1984年7月18日生まれ、北海道出身。映画美学校フィクションコース初等科修了後、一橋大学社会学部を卒業。 長篇デビュー作『Playback』(2012)がロカルノ国際映画祭インターナショナル・コンペティション部門に正式出品され、その繊細な語り口で注目を集めた。続く『THE COCKPIT』(2014)、『きみの鳥はうたえる』(2018)で確固たる作家性を示し、『ケイコ 目を澄ませて』(2022)が第72回ベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門に正式出品、『夜明けのすべて』(2024)も第74回ベルリン国際映画祭フォーラム部門に選出されるなど、国内外で高く評価されている。 最新作『旅と日々』は、ロカルノ国際映画祭のインターナショナル・コンペティション部門への13年ぶりの出品となり、日本人監督作品としては18年ぶりに金豹賞を受賞する快挙となった。三宅監督の作品は、人と人との関係、その間に流れる時間や空気を丁寧にすくい取り、観る者に“生きて、そこにいる”という実感と静かな感動をもたらす。
【制作経緯】読む人、読む瞬間で受け止め方が変容するつげ義春作品の謎、魅力に迫りたい

Q.本作はつげ義春さんの短編漫画「海辺の叙景」、「ほんやら洞のべんさん」が原作となっていますが、この2つを取り入れた背景をお聞かせください。 三宅監督 まずプロデューサーから(本作の)オファーをいただいたのは、2020年の夏頃だったんですが、そこから「 どの(つげ義春)漫画を自分は映画化したいと思うのか?」と、いろいろと考えて、ある時に『海辺の叙景』と『ほんやら洞のべんさん』の2本を組み合わせたいと提案をさせていただきました。
「海辺の叙景」、「ほんやら洞のべんさん」以外で特に意識した漫画『蒸発』
Q: 「海辺の叙景」「ほんやら洞のべんさん」以外で、つげ義春さんの漫画で意識されたり、参照されたりした作品があればお聞かせください。
三宅監督 いわゆる「旅もの」と言われる漫画は、どれも本当に繰り返し読みました。その中でも、特に『蒸発』という作品は強く意識しています。 また、つげさんご自身が『蒸発』について語られたり、書かれたりしているものにも、長い時間をかけて向き合ってきました。実は、その『蒸発』の要素を取り入れようと、脚本を書いていた時期もありました。最終的に、『旅と日々』には『蒸発』の場面が直接登場するわけではありませんが――。 『蒸発』の中には井上井月(いのうえせいげつ)※1という登場人物が出てくる場面があります。映画の中にその要素を入れたわけではありませんが、そこから考えたこと、受け止めたこと、解釈してきたことは、かなりこの映画の基盤になっていると思います。
※1:井上井月(1822〜1887)は、江戸末期から明治にかけて信濃の伊那谷を中心に旅を続けた俳人。自然や人生の哀しみを静かに詠み、素朴で人間味あふれる作風が特徴。芭蕉を敬い「信濃の芭蕉」とも呼ばれた。
読む人、読む瞬間で受け止め方が変わるつげ義春作品の謎をもっと知りたい

Q: つげ義春作品はセリフ量が多いわけではないですが、一コマ一コマの書き込みや、余白に膨大な情報が詰まっている印象を受けます。そのようなつげ義春作品を映像化する上で、意識されたことをお聞かせください。 三宅監督 そうですね。おっしゃる通り。僕はもともと、それほど漫画をたくさん読んできたタイプの人間ではないんですが、ついセリフを追ってしまうんです。次が気になるせいもあって、ついセリフを読んでしまう。 でも、つげ義春さんの漫画は、一コマ一コマが「ただの背景」ではなく、そこに何かを感じさせる。コマからコマへの移り変わりにも驚きがあるし、ページをめくった瞬間に「うわっ」と思わされるようなこともあります。さらに何度読んでも、そのたびに受け止め方が変わる。 たとえば『海辺の叙景』も、最初に読んだ時と今の年齢になってから読んだ時とでは、まったく印象が違いました。 それに、つげさんの漫画について書かれた批評やエッセイも多くあります。そういうものを読むと、自分とは全然違う受け止め方をしている人がいる。 つまり、自分の中でも読み方が変わるし、他の人の読み方もまったく違う。そのたびに「これって一体何なんだろう?」「その謎をもっと知りたい」というのがずっとありましたね。
【キャラ造形・キャスティング背景①】映画黄金期のスターのような光を放つシム・ウンギョンの魅力

Q: 李(演:シム・ウンギョン)のキャラクター造形とシム・ウンギョンさんをキャスティングした背景についてお聞かせください。 三宅監督 脚本を書いている段階では、当初は原作の漫画と同じように、(李は)日本人の男性として描いていました。ただ、それが理由かどうかは分かりませんが、だいぶ行き詰まっていた時期があったんです。 そんな時にふと「シム・ウンギョンさんがこの役を演じたら面白くなるんじゃないか」と思いついた瞬間があって。そのアイデアが生まれてからワクワクしたと言いますか、突破口になったんです。 後から考えてみると『ほんやら洞のべんさん』は、東京からやって来た人が宿の主人と出会う――それぞれが「よそ者」であり、全然違う人間が出会うことが“おかしみ”でした。 シム・ウンギョンさんが李を演じたことで、堤真一さん演じるべん造との間に共通点が何もなくなった。そのことで、ふたりが本当に「よそ者」である、という関係性がより際立ったように思います。 そして何よりシム・ウンギョンさんご本人が持っている資質――本当に稀有な存在感といいますか――それが、つげ義春さんの漫画に登場する人物たちの持つ、あの稀有な存在感とどこか共通しているように思います。 シム・ウンギョンさんだったからこそ、この映画の美しさ、あるいは軽やかさになったと感じています。
シム・ウンギョンさんと準備段階で積み上げた李役のイメージ

Q: シム・ウンギョンさんの撮影時の印象的なエピソードについてお聞かせください。 三宅監督 シム・ウンギョンさんは本当にプロフェッショナルな方でした。撮影している最中、ふと「かつての映画の黄金期の大スターを撮っているときの感覚は、このようなことなのでは?」と思う瞬間があったんです。いろいろな光をスクリーンで跳ね返すような、「本当に輝くような人だな」と感じました。 撮影の準備段階では、メールのやり取りを重ねながら、一緒に役柄を作り上げていくプロセスがありました。たとえば彼女の方から「太宰治は近いですか?」というメールが来て、僕が「自分が思っている太宰の印象とは違うと思う」と返して。 そうではなく「立原道造※2:という詩人・建築家の方が少し近い気がする」と話をしたり。あるいは彼女からも韓国の詩人を教えてもらうこともありました。
それからサイレント映画――特にバスター・キートンやチャップリン――の話を共有できたことも、この映画を作っていく上でとても役に立ちました。
※2:立原道造(1914〜1939)は、昭和初期に活躍した詩人であり、建築を志した芸術家。東京帝国大学で建築を学ぶかたわら、夢や憧れ、自然への想いを繊細な言葉で紡いだ。代表作『萱草に寄す』などには、青春の儚さと清らかな感性があふれている。
【キャラ造形・キャスティング背景②】河合優実と積み上げた渚の「からっぽ」というキーワード

Q: 夏編の渚(演:河合優実)のキャラクター造形と、河合優実さんのキャスティングの背景についてお聞かせください。 三宅監督 『海辺の叙景』を映画化しようと決めた時点で、河合優実さんの事務所とは以前から面識があったので、かなり早い段階で彼女のスケジュールを問い合わせて、「こういう企画があるんです」とお伝えしました。まだシナリオができるか、できていないかくらいのかなり早い段階でお声がけさせていただきました。 実はずっと以前、一度オーディションでお会いしていました。その時はご一緒することは叶わなかったのですが。「一緒に仕事をしてみたい」という思いもありました。

河合さんと話していたのは、そうですね――一言で言えば、「都会での日々の人間関係に完全に疲れきって、すべてを放り出して空っぽになりたい」と思って旅に出ているということでした。 もちろん、旅に出たからといってそう簡単に空っぽになれるわけではない。けれど「とにかく“空っぽの状態でその場にいる”ということが重要だね」と話していました。 この「空っぽ」という言葉は、確か彼女の方から出てきたキーワードだったと記憶しています。実際に神津島での撮影に入ってからも、もちろん「このシーンではこうしよう」といった基本的な計画はお互いにありました。 それでも最終的には、それらを一度捨てて、本当に“その場”“その瞬間”の出来事に対して、空っぽの状態でいる。だからこそ、何かを受け取ったり、反応できたりする。河合さんはまさに、そういう存在としてカメラの前に立ってくださったように思います。
原作にはない渚の設定、指に包帯の演出意図

Q: 渚の指に怪我があるのは、原作にはなかった設定ですが、脚本時点で組み込まれていたのでしょうか? 三宅監督 指の包帯は脚本の段階で入っていました。ただ、ビジュアル面で悪目立ちしてしまわないかという懸念はあったので、実際に撮影地で衣装を着た状態で包帯を巻いてみてどうか、現場で確認するまでは保留にしていました。 脚本を書いた時点では、「空っぽになる」といっても、そう簡単にはなれない――その“居心地の悪さ”のようなもの、“自分の身体に対する不快感”、あるいは"自分自身に対する不快感”。そうしたものを意識するためのポイントとして、包帯が演技の助けになるならばと思って、脚本の段階で書いていた気がします。
【キャラ造形・キャスティング背景③】扉を開けた瞬間に感じた髙田万作の夏男らしさ

Q: 夏編の夏男(演:髙田万作)のキャラクター造形と、髙田万作さんのキャスティング背景についてお聞かせください。 三宅監督 髙田万作さんとは、オーディションで会いました。ドアを開けて入ってきた瞬間から、すでに“(夏男)役らしさ”のようなものを強く感じていました。 実際にセリフを声に出してもらったとき、その声が本当に素敵で――その日のうちに「ぜひ夏男を演じてほしい」とオファーをしました。 つげ義春さんの漫画のセリフを声に出すのは非常に難しい気がしていたのですが、髙田万作さんが見事に演じてくれたと思います。
衣装を選ぶことから手繰り寄せていった夏男の人物造形

Q: 海に馴染んでいない夏男のファーストカットが印象的でした。髙田万作さんの撮影時に印象的だったエピソードについてお聞かせください。 三宅監督 衣装合わせの時には、靴からシャツまでいろいろと試していくのですが、その中で印象的だったのは、彼が「これはしっくりくるな」とか、「これは少し違うと思う」といった率直なアイデアを出してくれたことでした。 東京の会議室で衣装合わせをしながら、海辺での状態を想像するというのは本来とても難しいことではあるのですが、彼とはまず“衣装を選ぶ”というところから一緒に感覚を手繰り寄せ、探っていけた、というのが非常に印象深かったですね。
【キャラ造形・キャスティング背景④】無言でも滲み出る堤真一の"べん造”としての佇まい

Q: 堤真一さんとご一緒された印象についてお聞かせください。 三宅監督 堤さんとは一緒に仕事をして、本当に「超好き、大好き」と思うようになりました。もちろん俳優としても非常に尊敬していますし、こういう言い方が失礼でなければ――単に“俳優”という職業を超えて、今の日本に生きている“社会人”というんですかね、そういう先輩として、すごくかっこいい方だな、素敵な方だなと思いました。
あの土地、あの宿に馴染むことが必要だった

Q: 三宅監督はべん造役として堤真一さんに求められていたことをお聞かせください。 三宅監督 言葉にするのは非常に難しいんですけれども、あの土地に馴染むこと、そしてああいった宿に馴染むことが必要だと思っていました。同時に、そこには“可笑しみ”のようなものも滲み出てほしかった。 堤さんはしゃべる時も、あるいは無言の時でも、佇まいとして説得力も、悲しみも、可笑しみも、すべてを全身で表現してくださったと思います。
【撮影秘話】三宅監督が初めて決断・経験したまるごとリテイクしたシーンとは?

Q: 堤さんとのシーンで、三宅監督は本作品で初めて“シーンをまるごとリテイク”されたと伺いました。その理由についてお聞かせください。 三宅監督 今回“シーンまるごと”を後日にもう一度やり直すということをしました。今までは「あるカットだけもう一度撮らせてください」という経験はありましたが、それなりに長いシーンを撮影序盤に撮って、他の場面を撮り進めていく中で「やっぱり序盤をもう一度やりたい」と思うようになって。 もちろん、それはとてもプレッシャーのかかることでしたし、難しい判断でもありました。 堤さんとウンギョンさんにその提案をしたところ、ふたりが最初にそのシーンを撮った時にどう感じていたか、そしてその後撮影を進めるなかで「確かにこう変えたら、もっと面白くなるかもしれないね」と一緒に台本を並べて、鉛筆で「このセリフはいらなかったね」とかもう一度台本をブラッシュアップして撮影することができました。 それは「一緒にものを作った」という実感をより強く得られましたし、本当にありがたかったです。
セリフを削ぎ落とし、べん造をより豊かで深みのある人物に
Q: リテイクされた具体的なシーンや描写を伺ってもよろしいでしょうか。 三宅監督 (シーンとしては)シム・ウンギョン(李)さんが宿に来て、最初の晩に囲炉裏を囲む場面です。 最初のセリフで「この宿は一体いつからあるんですか?」と尋ねて、「わからねえよ、昔からだろ」、「昔からというのは?」「いや分からねえ」というようなやりとりがあるのですが、あのシーンは、もともとはもっとセリフがあったんです。 べん造さんも、もう少しあれこれと話していたのですが、それをだいぶ削ぎ落としました。 ただ単にセリフを減らしたということではなくて、べん造という人物の“存在感”や、どこかミステリアスな部分を含めてより豊かになったかなと思っています。
【撮影秘話】渚と夏男が海で泳ぐシーンは"迫力”が必要不可欠だった
Q: 夏編で、渚と夏男が海で泳ぐシーンがとても印象的でした。このシーンの撮影エピソードについてお聞かせください。 三宅監督 実際に海で撮影をしています。どれくらい深いところで撮ったのか?、あるいは浅いところだったのか?を明かしてしまうと、すこし冷めてしまうので言いませんが。 ただ、このシーンには“絶対的な迫力”が必要でした。海の撮影で何より重要なのは、その迫力をどう出すか。そして「怖い」と思わせる必要がある。 実際つげさんの漫画を読むと怖いので、それを捉えるためにあれこれとしました。撮影期間全体で島に滞在したのは9〜10日だったのですが、あの終盤の海のシーンだけで3日間をかけています。撮影行為そのものとしても、あの場面はハイライトでした。
【撮影のテーマ】コントロールできない事象をどう捉えるか?

Q: 山や海など、コントロールできない自然の美しさや“奇跡のようなショット”が印象的でした。その撮影でこだわった点についてお聞かせください。 三宅監督 おっしゃる通り「コントロールできない天気をどう撮影するか?」というのが今回のテーマのひとつでした。自分のわがままなリクエストもいろいろとあり、たとえば「序盤は絶対に晴れていてほしい」「少しずつ曇って、最終的には雨の中で終わってほしい」とかなり強く考えていました。 そのためにできることといえば天気予報の確認と、実際には雨雲レーダーにも反映されない天気の変化もありますから。そうしたものをつぶさに見ながら、チーム全体で臨機応変に対応していく――そこがとても重要だったと思います。 本当にラッキーなことがたくさんありました。スケジュールを組んでくれた演出部の松尾崇さんの力が非常に大きかったですし、それに応じて臨機応変に動いてくれたチーム全体の力があると思います。
【音へのこだわり】つげ義春作品特有の直感的な"怖さ”を音で表現

Q: 波の音や風の音、虫の声などの音や音楽も本作の重要な要素だったかと思います。その点でこだわった部分をお聞かせください。 三宅監督 つげさんの漫画『海辺の叙景』は途中からどんどん不穏になって、理屈抜きに怖くなっていきます。ページをめくった瞬間に「何かやばいことが起きている」という直感的な怖さがある。それって、音でこそ体感できるものなんじゃないかと思ったんです。だから、観ている人が音に敏感になるような作りにしたいという意識がありました。 音楽を担当したHiSpecも素晴らしいテーマを作ってくれたので、ゴージャスなものになったと思います。
【オープニングの演出意図】セリフなしのOP5分、最初のセリフが「Ciao」であることのおかしみ

Q: 本作はオープニングからセリフのないシーンが連なり、約5分ほど経過してから言葉が出てきます。オープニングシークエンスで意識された演出があればお聞かせください。 三宅監督 初めからそうしたいと思っていたわけではなく、結果的にそうなった、という感じでした。編集のある段階で見返した時に、「おー、こんなに前半で誰も喋らないんだ」と自分でも驚きました。 さらに、最初に出てくる冒頭のセリフがイタリア語の「Ciao(チャオ)」ですから(笑)。自分たちでも「可笑しいな」と思いながらやっていたんですが。“映画を観る面白さというものが”純粋に冒頭にあればよいなというところですかね。
【劇中劇の構造】映画で何度も“驚く”という経験を生み出したかった

Q:夏編は“映画内の映画”というメタ的な構造に入ると思います。ただ、途中で挟み込まれる李さんや上映会のショットに切り替わるまで、劇中劇であることを忘れてしまうほど夏編の世界に没頭していました。他の一般的な作品では劇中劇は意識的にフィクション性を強調する(または、強調されてしまう)ことが多いように思いますが、その点で監督が意識されたことはありますか? 三宅監督 まず前提として「映画を観ながら何度も“驚く”という経験を作り出せたらいいな」という思いがありました。 劇中劇という構想も、そこから生まれたものです。自分自身、これまでいろいろな映画を観てきて、いろいろな驚きをしてきたわけですが。たとえば、「あ、これは映画だったんだ」と観ている途中でふと気づく瞬間。 人と人が激しく戦っているシーンでのめり込んで観ているのに、カメラが突然ロングショットに切り替わる、カーチェイスの最中に突然「ポーン」と遠くからのショットに切り替わる瞬間、何か違う感覚になる、そういう驚きを今まで経験してきました。 「これは映画だよね」とすごい意識しているのに、登場人物がトラブルに巻き込まれて本当に苦しくなったりとか何か夢中になっていく。 「映画の中に入ったり、出たり、入ったり、出たりしていく。」というのがすごい面白いなと思いましたね。 例えるなら、夢を見ている時に「ああ、これは夢だな」と気づいても、またそれを忘れて夢の中で本気になってしまう。そして目が覚めた時に、「あれ、本当に夢だったのか?」「これ本当に昨日の出来事じゃないのか?」「いや、でも夢か」――と曖昧になる感じです。 そのような感覚を、この映画の中で経験してもらえたら面白いんじゃないかと思いました。そのためには、おっしゃるように“生々しさ”や“艶やかさ”“色っぽさ”といったものがとても重要だと思いました。 なので、ものすごく良い風が吹く、あるいは俳優たちの存在感、“個別の肉体”といいますか――。そうしたものをどう撮るかということがすごくよい挑戦でした。
【三宅唱監督が考える“映画の本質”】日常の隙間に潜むものを発見する――その瞬間の“驚き”

Q: つげ義春さんが漫画の本質を追求したように、三宅監督も“映画の本質を追求したい”とおっしゃっていました。三宅監督の考える“映画の本質”をお聞かせください。 三宅監督 「本質」なんていう厄介な言葉を使ってしまった自分を、本当に後悔していまして(笑)。最近は撤回したいとさえ思っていました。 映画の本質は正直分かりません。ただ自分が「いろいろな映画を観てきて“共通して面白い”と感じることは何か?」という程度で考えて、それは“驚くこと”なんじゃないかと思います。 映画を観ていると、普段気づいていないことに「あ、こんなことなんだ」と思う――それが映画を観る面白さだと思うんです。 きっと、観たことのないものを観たいからこそ、映画館に行くと思いますし、そして同時に、映画を観ることで「自分は普段の生活で、いかに色々なものを見逃しているんだな」と気づく、発見する驚きや楽しさが映画にはあると思います。 それが、もしかしたら疲れているときにこそ“生きている実感”のようなものに繋がれば、それは映画の持つ力なのかなと思います。
映画『旅と日々』は2025年11月7日より公開中

『旅と日々』は、つげ義春の作品世界に深く触れながらも、その世界をそのまま再現するのではなく、“今”という時代の映画として新たに“生き直す”ような作品です。 三宅唱監督が大切にされている「驚く」という感覚。つげ義春の原作が、読むたびに異なる印象を与えてくれるように、三宅監督の『旅と日々』もまた、観るたびに新しい感覚と体験をもたらしてくれます。 この映画でしか味わえない体験があり、そして映画を観る“喜び”と“幸せ”を、この上なく与えてくれる――そんな唯一無二の傑作です。 映画『旅と日々』は、2025年11月7日より全国公開中。音と映像、そして空気までもが溶け合う劇場空間で、ぜひその全身をもって体感してください。 ▼取材・文:増田慎吾
![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)