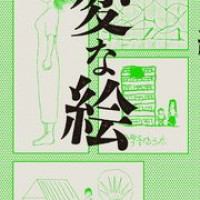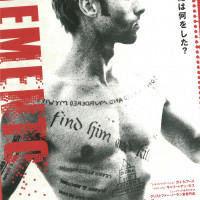『国宝』歌舞伎の演目を一覧で解説!連獅子や鷺娘が劇中で意味するものとは?

2025年6月6日から公開され、邦画の興行収入ランキングを塗り替える大ヒットを続けている『国宝』。この記事では、本作の劇中で演じられている歌舞伎の演目を紹介し、あらすじ・見どころなど解説していきます。
『国宝』に出てきた歌舞伎の演目を解説

映画『国宝』は、吉田修一の同名小説を原作とした歌舞伎役者の半生を描く「芸道映画」。のちに「国宝」となる主人公の歌舞伎役者・喜久雄を吉沢亮、そのライバル・俊介を横浜流星が演じました。 3時間と長丁場である本作では、物語の展開に符合した内容の歌舞伎演目が要所要所で演じられます。 ここからは劇中に登場した歌舞伎の演目を一覧で紹介。あらすじや見どころとともに、物語とどのように符合し、どんな意味を持っているのかを解説していきます。
「関の扉」(せきのと)
樹齢300年を超える桜の木「小町桜」がある逢坂山で暮らす、政変に巻き込まれた亡き帝の忠臣・宗貞。ともに関を守る関兵衛は実は天下を狙う大悪人・大伴黒主であり、大願成就するという吉相が出た占いによって小町桜を切り倒そうとします。 劇中で演じられたのは、小町桜の精である遊女・黒染と関兵衛が出会う場面。本作の冒頭、ヤクザの新年会の余興として登場し、喜久雄が黒染を幼いながらも妖艶に演じていました。上方の歌舞伎役者・花井半二郎に女形の才能を見出され、のちに芸養子として引き取られることになる重要な場面です。
「二人藤娘」(ふじむすめ)
近江・大津にある松の大木に絡みついている藤の花に現れた2人の娘。藤の花の精である娘たちは、浮気性な男心と切ない女心を語り合いつつ、近江八景の歌に合わせて踊り出します。満開の藤の花の下で踊り、度々変わる衣装も華やかな舞踊作品です。 良きライバルとして切磋琢磨してきた喜久雄と俊介が初めて舞台で共演する演目として選ばれていますが、若い2人の才能を見せるには初々しく明るい最適な演目。この初舞台の成功によって2人は有力な興行主の目に留まり、京都南座の大舞台に上がる機会へ繋がっていきます。
「連獅子」(れんじし)
「獅子の子落とし」の伝説をもとにした舞踊作品。親子の獅子の精が霊山・清涼山の石橋で牡丹の花と戯れて踊る様を通して、親子の情愛と継承を表現しています。豪快に長い毛を振り回す「毛振り」や、親子獅子の息の合った演技が見どころです。 実際の親子で演じることも多い演目であり、劇中でも半二郎が俊介と演じていました。喜久雄が半二郎に引き取られて初めて見る歌舞伎演目として、かなり重要な意味を持っています。ここで、名門一家の跡取りである俊介と、芸養子として後ろ盾も血筋もない喜久雄との決定的な立ち位置の違いを見せつけているのです。
「二人道成寺」(どうじょうじ)
平安時代の「安珍清姫伝説」をもとにした、女形舞踊劇の最高峰といわれる演目。恋に破れた女が大蛇と化し、鐘に隠れた男を鐘ごと焼き尽くしたという伝説がある道成寺が舞台です。この演目は鐘が再興され、供養に訪れた白拍子が実は女の霊だったという後日譚となっています。 劇中ではこの演目が2回演じられており、1回目は京都南座でのメジャーデビュー公演、2回目は喜久雄の歌舞伎界復帰公演と、2人の成長と絆を感じさせる演出が際立っています。 南座公演は大成功を収め、喜久雄と俊介が次の歌舞伎界を担う若きスターコンビとして売り出されていきます。一方復帰公演では2人が「ただひたすらに共に夢を追いかけた」というキャッチコピーさながらに、辛酸を舐めた2人の成熟した姿を見せて対比していました。
「曽根崎心中」(そねざきしんじゅう)
江戸時代の浄瑠璃から歌舞伎となった男女の心中物語で、知名度の高い演目。醤油屋の手代・徳兵衛とその恋人の遊女・お初は、徳兵衛から金を騙し取った九平次と対峙することに。しかし九平次の悪巧みが明らかになった時にはすでに、2人は心中しようと曾根崎へ向かっていました。 劇中では最大の見どころである、お初が徳兵衛に死ぬ覚悟を問う場面と曾根崎へ向かう2人が登場。やはり2回演じられており、1回目は半二郎の代役に喜久雄が指名され俊介が姿を消した時、2回目は病に倒れた俊介の最後の公演として選ばれ喜久雄が徳兵衛を演じました。 この2回の対比も素晴らしく、喜久雄のお初と俊介のお初両方を見せることで2人の因縁と執念を表現しています。さらに2人がともに芸道に命を捧げた様をこの演目で暗喩し、特に2回目はまさに2人で芸道に「心中」したかのような圧倒的迫力を持っていました。
「鷺娘」(さぎむすめ)
人間の男に恋をした鷺の精が若い娘に姿を変えて、その恋心を表現する舞踊劇。しかし恋は成就することなく、再び鷺の精に戻って地獄の責苦に苦しみながら、雪が降り積もる中で息絶えてしまいます。初めは白無垢姿で登場し、最後は鷺の精の姿で美しくも哀しく儚い舞で魅了します。 劇中では田中泯演じる万菊が踊る舞台を喜久雄が観劇する場面で登場。そして人間国宝となった後初めて喜久雄が踊った演目が「鷺娘」でした。“悪魔と取引して”までも芸道に執着した喜久雄が到達した点が、この演目だったのです。 2回演じられた「鷺娘」の意味も重要で、ここにも継承と血筋の因縁が表現されています。鷺娘は喜久雄にとって万菊から受け取った継承の証だったといえるでしょう。
『国宝』で登場した歌舞伎演目を解説しました!

映画『国宝』に登場した歌舞伎演目をおさらいしてから、再度鑑賞してみればきっとさらなる発見があるはず!演目と物語が絶妙に符合した演出も大きな見どころですので、ぜひまた劇場に足を運んでみてください。
![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)