【小野寺系】アニメ版「打ち上げ花火」が打ち立てた新たな“青春”とは

アニメ映画『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』は何を描いたのか?

「平べったい?それとも丸い?」 打ち上げ花火を横から眺めるとどう見えるのかという、子どもたちの疑問から起こる騒動と、大人びた少女に魅せられる少年の夏の一日をノスタルジックに描いた、岩井俊二監督による青春ドラマ『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』。伝説となったこの作品が、24年経って劇場アニメ作品として甦った。 社会現象となった『君の名は。』で企画・プロデュースを担当した川村元気が再びたずさわったアニメ作品ということもあって、「ブーム再来か?」と思われた本作だが、完成したものはそのような内容を期待する観客のイメージとは異なり、さらには原作ドラマともかなり違ったものになっていた。 それでは、『君の名は。』や「打ち上げ花火」原作ドラマと、本作はどう異なっているのか。それぞれの作品と比較しながら、難解な印象も与えられる本作の描いたものを、この記事では深く掘り下げていきたい。
2つの「打ち上げ花火」、全てはTVドラマから始まった

岩井俊二監督の『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』は、1993年にTVドラマ『if もしも』の1エピソードとして放映された。この半年ほど続いた1話完結型のドラマシリーズは、毎回ドラマの途中で主人公に二つの選択肢が示され、そこでの選択によって展開や結末が異なっていくストーリーを、両方とも描くという実験的な要素のあるものだった。 比較的軽いテイストのエピソードが多い中で、『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』は、とくに映像の完成度が圧倒的で、TVで見られるドラマとは一線を画するものになっていた。そのみずみずしい映像表現は、日本の青春映画の名手であった相米慎二監督が出現したインパクトに近かったと言っていいかもしれない。 当時リアルタイムで見ていて良く覚えているが、「一体、自分の見ているものは何なんだ!?」と、インターネット検索もできない時代、このドラマはしばらくの間、私の中で謎として残っていた。
岩井俊二監督のオリジナル版「打ち上げ花火」は会心の一作

ヒロイン・なずなを演じた奥菜恵が、当時14歳ながら異様な妖艶さを発揮し、山崎裕太が演じる典道(のりみち)など、少年たちの心を翻弄していく。夜空を彩る花火、転校していく少女、そしていつかは大人になる子どもたち……。これらは、青春がはかなく一瞬で過ぎ去ってしまうことを示す象徴として描かれている。 この作品は、TVドラマとしては異例ながら、日本映画監督協会新人賞を受賞し、あらためて映画作品として上映もされた。その後、岩井監督は映画監督として、やわらかな照明と繊細な映像加工が生み出す美しい映像によって若い世代に熱狂的な支持を受け、とくに90年代後半から00年代初頭までカリスマ的な人気を誇った。 岩井監督の『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』は、そこに至る道を切り拓いた伝説的な作品でもあるのだ。
アニメ版「打ち上げ花火」、岩井俊二版からの設定変更の数々

アニメ版である本作がオリジナルから大きく変化したのは、子どもたちのキャラクター設定を、小学生から中学生に変えたという部分である。これによって、なずなと主人公・典道の「駆け落ち」や妄想渦巻く世界の表現など、本作の恋愛感情はより粘着的でリアリティを感じられるものになっている。 その反面、オリジナル作品にそのまま沿った子どもっぽいセリフの数々や、「打ち上げ花火は平べったいか丸いか」という子どもならではの疑問には、少し無理があるようにも思えるのも確かだ。 原作ドラマでは、なずなと典道の二人が夜のプールに忍び込みはしゃぐシーンが印象的だが、ここでREMEDIOSの『Forever Friends』が流れるように、男女としての恋愛関係に限界が生じるという、小学生ならではのせつなさが、本作では感じられなくなっているのも確かである。
アニメ作品としての『君の名は。』との違いとは?

さらに少年たちはみんなちょっとイケメン風に解釈され、原作を見ている観客からすると親しみにくいデザインになっていたのは残念だ。彼らが着ている学校の制服についても美少女アニメ風の独特なセンスで、一般性に欠ける部分があり、このあたりは、『君の名は。』のキャラクターデザインをした、スタジオジブリ出身の安藤雅司による幅の広さが際立つところである。 全体的に安定したクォリティを感じる『君の名は。』に比べ、本作は部分的に作画が不安定な部分も見られる。だがヒロインの媚態を中心に、アニメーターが力を発揮できる箇所では、『君の名は。』をはるかに凌駕するところがいくつも見つけられる。このようなペース配分や快楽原則に沿っていく部分というのは、アニメーションスタジオSHAFT(シャフト)ならではの姿勢であろう。 本作が『君の名は。』ほど幅広い支持を受けていない理由は、ヒロインの描き方にもあるだろう。『君の名は。』では男女の主人公たちが、同等の親しみやすさを持っていたのに対して、本作のヒロイン・なずなは劇中で男を破滅させる魔性の女(ファム・ファタール)としての役割を持たされている。人によっては反感を持つ場合があるだろうし、劇中で典道が作り出す男子学生の思春期の鬱屈からくる身勝手な妄想にも、反発する向きがあるかもしれない。
アニメ「打ち上げ花火」が到達した、青春映画の先進的解釈

しかし、これが新房昭之監督の作家性の真骨頂といえるのも確かだ。本作では、選択をやり直すたびに、世界がねじ曲がり異様な姿になっていく。 新房監督の過去作で、登場人物の個人的な愛情から、時間を超えて世界をやり直し続けるという描写があったように、ここでも都合よく世界を作り変えようとする、不気味ともいえる個人的で身勝手な想いが、作品に暗いパワーを与えることに寄与している。 このような、二人だけのために世界があるという極端な表現を、いわゆる「セカイ系」と呼ぶ向きがある。その先駆けのひとつとなったのはアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』だが、私見では、その萌芽はすでに、永井豪の漫画『デビルマン』の最終回における、人類が絶えて二人きりになった最終決戦後の渚の風景にあったように思われる。 本作で最後にたどり着く二人だけの渚には、その表現が重ねられているように見える。
セカイ系アニメの始まり、『銀河鉄道の夜』の列車
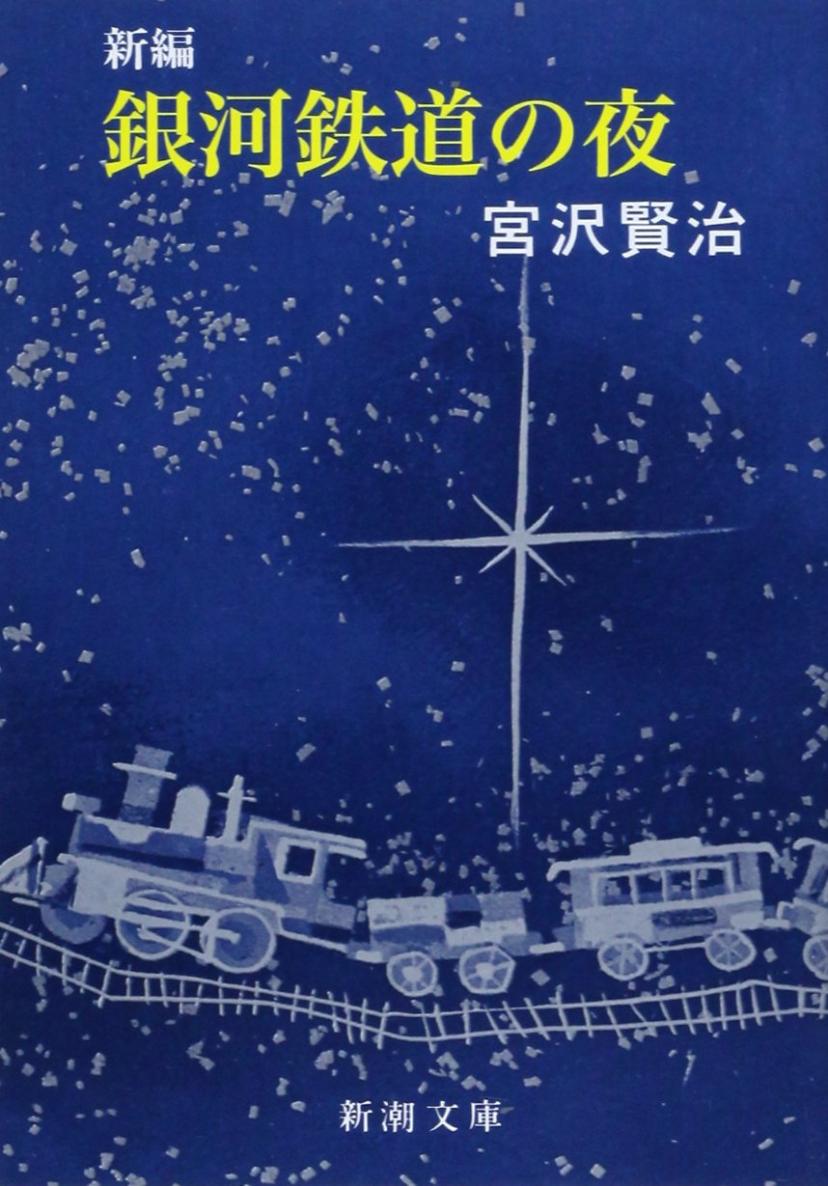
さて、さらにそのような表現のルーツを遡ると、宮沢賢治の児童文学『銀河鉄道の夜』に突き当たる。本作でも、典道たちが乗り込んだ列車が、あり得ない方向に向けて走り出す超常的なシーンがある。『銀河鉄道の夜』は完成までに4つのバージョンで書かれたが、「第3次稿」には、主人公ジョバンニとブルカニロ博士という人物の間で、こんなやりとりがある。 「あのひとはね、ほんたうにこんや遠くへ行ったのだ。おまへはもうカムパネルラをさがしてもむだだ。」 「ああ、どうしてさうなんですか。ぼくはカムパネルラといっしょにまっすぐに行かうと云ったんです。」 「あゝ、さうだ。みんながさう考える。けれどもいっしょに行けない。そしてみんながカムパネルラだ。おまへがあふどんなひとでもみんな何べんもおまへといっしょに苹果(りんご)をたべたり汽車に乗ったりしたのだ」

これは、宮沢賢治が創造した「銀河鉄道」の正体が暴かれる場面である。銀河を走る鉄道とは、賢治が信仰していた仏教思想に根ざした「輪廻転生」の考えをモデル化したものだ。「輪廻転生」とは、「悟りを啓き仏となって涅槃(天国)に至るまで、何度も生と死を繰り返して、生命の循環を繰り返さねばならない」という概念である。 つまりジョバンニは、何度も何度も死んでは蘇り、別の人間になって、また別のカムパネルラと出会い、「ほんとうの天上(涅槃)」へと向かい、いつまでも一緒に行こうとするのである。
アニメ版『打ち上げ花火、下から見るか?横から見るか?』で描かれた二人とは

何度も何度も分岐を繰り返し、世界を変質させながらいつまでもなずなと一緒にいたいと願う典道。彼にとってなずなは、旧約聖書における"イブ"であり、仏教において人々を涅槃へ導くという菩薩であり、『銀河鉄道の夜』のカムパネルラであり、『デビルマン』におけるサタンである。 本作はこの関係性を、岩井俊二監督の青春映画を解釈し直すことで、再現したのである。青春映画という題材をここまで根源的なものに作り変えたという部分は、特筆すべきである。 この他にも、不思議な力を持つ珠や、謎の死体の描写など、まだまだ本作には掘り起こすに足る箇所が存在する。この記事を読んでいるあなたも、"夏の迷宮"にふたたび入り込んで、思いをめぐらしてみてほしい。
![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)

















