【小野寺系】Netflix版『デスノート』が最高の青春こじらせ映画に仕上がった理由

アメリカ版「デスノート」がついに配信!
名前を書けばその相手を殺せるという、死神のアイテム“デスノート”を手に入れた男子学生が、“新世界の神”を目指して大量に死の裁きを下していくという、日本のダークな人気漫画『デスノート』が、Netflix配信作品として、ついにアメリカで映画化された。 週刊少年ジャンプ連載漫画の映像化といえば、後に脚本家が個人的に謝罪するまでに至った失敗作として知られる『DRAGONBALL EVOLUTION』をつい思い出してしまうが、本作『Death Note/デスノート』の出来は果たしてどうだったのだろうか。実際の作品の内容や、日本の実写作品も振り返りながら検証していきたい。
これまでの日本での実写版は
『DRAGONBALL』のような、ファンタジー色や人間の限界をはるかに超えたアクションを表現するのは至難の業だが、『DEATH NOTE』は頭脳や心理のバトルが展開するクライムサスペンスとしての面が大きいため、比較的映像化しやすい題材だ。それが何度も『DEATH NOTE』が映像化できた理由であろう。
最初の実写映画『デスノート』前・後編
金子修介監督による前・後編2作の実写映画は、前編を後編公開にあわせてTVで放映するという異例の宣伝方法も功を奏し、日本国内で合わせて興行収入約80億円を記録するヒット作となった。金子監督はもともと漫画への理解が深く、漫画原作の実写化に長けていたということもあり、ポップな表現やケレン味の効いた演出が題材にマッチしていた。さらに“L(エル)”を演じた松山ケンイチは、この作品が出世作となったように、抑揚のないトーンで不自然な箇所で息継ぎをする印象的な喋り方も素晴らしく、彼の代表作の一つとなっている。
スピンオフと続編映画
その人気を受けて作られた、“L”を主役としたスピンオフ映画『L change the WorLd』は、原作漫画には描かれなかった映画オリジナル作品ということもあって、作品本来の強みを活かせなかった面が大きい企画だ。 さらに2016年に製作された、東出昌大、池松壮亮、菅田将暉の3人をトリプル主役を迎えた『デスノート Light up the NEW world』もオリジナル脚本で、複数のデスノートを使った新しい展開が意欲的な作品だったが、奇を衒ったぶん無理のある部分もあったように思われる。
TVドラマ版『デスノート』
Vドラマ版では、 “夜神月(やがみ ライト)”を演じた窪田正孝の演技が見どころだった。映画版では見られなかった、原作漫画の鬼気迫る狂気の場面を地上波で表現し得たという点で評価できる作品だ。
実写化作品への拒否反応
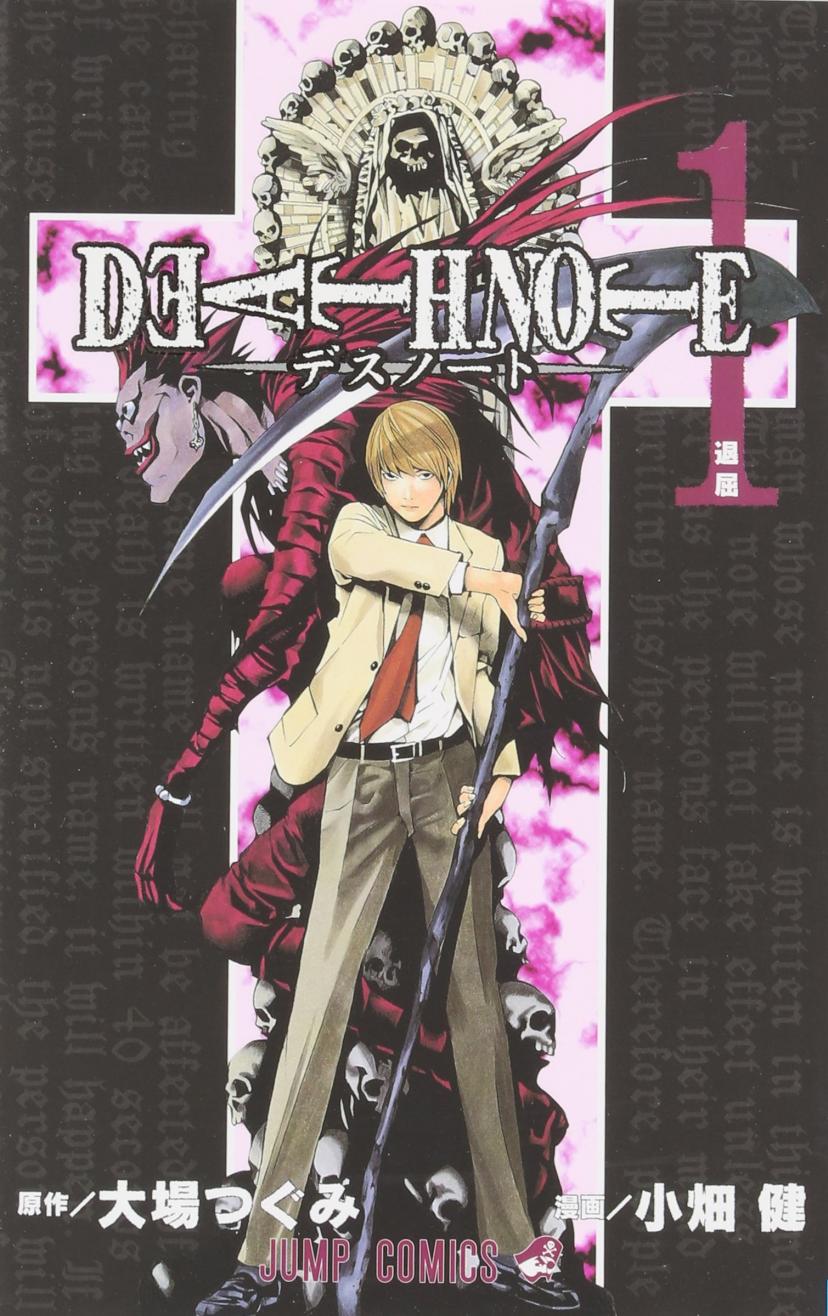
ただ、これらの作品は、公開当時それぞれに一部の原作ファンからの強烈な拒否反応があったことも事実だ。人気がある作品、とくに漫画やアニメが実写化されると、理不尽なくらいに強い批判を浴びせられることがある。だが新しい実写版が作られると、口々に「前の実写化作品は良かったのに」などと言われたりするように、知らぬ間に評価が高まっていることが多い。そういう意味もあって、こういう作品では公開当時の反応を冷静に見極めた方が良いだろう。
アメリカ版『Death Note/デスノート』の圧倒的映像
さて、今回のアメリカ版『Death Note/デスノート』。日本の映画版が前・後編2作品で制作費約20億円だったのに対し、本作はこれ1作だけで約50億円かけている。それだけに、各シーンのヴィジュアルは圧倒的に勝っている。死神が初めて登場する場面や、主人公が雨の中で不良学生に殴られるようなシーンでさえも、画面の密度が濃く、映像の完成度が飛躍的に高まっている。
原作のキャラクターはどう変わったのか
アダム・ウィンガード監督の発言によると、本作は現代のアメリカという環境下でデスノートが存在したら一体どうなるのか、そして描かれるべきテーマは何かということを改めて考え直した作品なのだという。本作は原作の骨格を部分的に残しつつ、様々な要素をいったん解体して、アメリカの文化や監督の作風に合わせて再構築するという試みをしている。したがってキャラクターの設定も、それにともない修正された。
ライト・ターナー/頼りない等身大の高校生
ライト・ターナー(Light Turner)は、デスノートによって力を得るまでは頼りない秀才タイプの学生だった。アメリカの典型的な高校では、こういうガリ勉は人気がない場合が多い。演じるのは、ミュージシャンで子役出身のナット・ウルフ。母親を殺され、殺害した犯人に復讐するためにデスノートを使うなど、当初は共感できる人物として描かれ、青臭い正義感や承認される欲求を持つ人物像は、今までの実写化作品のなかでは最も等身大でリアリティがある。
リューク/危険で不気味な死神
デスノートの所有者に取り憑く死神リュークは、雰囲気がそっくりのウィレム・デフォーが声を担当している。またヴィジュアルでは、演技者の動きを基にCG技術や照明の効果によって、さらに不気味な存在として描かれている。その存在を疎ましく思ったライトが「お前の名前をノートに書いてやる」と脅すと、「やってみな。今までの所有者のなかで俺の名前を書こうとした奴もいたが、いいとこ二文字までしか書けなかったな」と返すなど、そのやりとりはいつも緊張感が漂う。ちなみに、日本語吹き替え版では、日本のアニメや実写映画版と同じく中村獅童が声を演じている。
"L(エル) "/熱い心を持つ危うい天才
ライトを追いつめる世界的名探偵“L(エル)”を演じるのが、アフリカ系の俳優でラッパーでもあるキース・スタンフィールドだ。『ストレイト・アウタ・コンプトン』では、スヌープ・ドッグの役を担当していて、今回は意外な配役にも思えるが、その細く華奢な体つきには、常人離れした能力を持っていそうな説得力がある。頭の良さと不安定な感情が危うく成立している雰囲気が魅力的だ。
ミア・サットン/殺人ゲームに熱心なチアガール
『パロアルト・ストーリー』でナット・ウルフとすでに共演しているマーガレット・クアリーが演じるヒロインは、弥海砂(あまね ミサ)を参考にしたと思われる、ライト・ターナーの恋人“ミア・サットン(Mia Sutton)”役だ。高校のチアガールだったミアは、ノートによる殺しに積極的で、ライトをむしろ殺人に引き込んでいく役割を担う。
「ホワイトウォッシュ問題」とは
本作『Death Note/デスノート』は、主演など多くの俳優が白人に置き換わっていることから、「ホワイトウォッシュ」を指摘されている一作である。これは、本来の人種を差し置いて、役を白人に置き換えることを指す、人種差別を問題にした言葉だ。これを日本人が聞くと「アメリカ人には白人が多いのだから、白人俳優が演じるのは当然だ」という意見や、「日本人はそんなことを気にしたりはしない」という意見が出ることがあるが、別に日本人に配慮しているわけでなく、アメリカにおけるアジア系の俳優など、特定の人種の職を奪う行為として、この現象は、近年とくに社会問題化しているのである。 本作は“L”に黒人俳優、その“L”を補佐するワタリに、日系の俳優・声優のポール・ナカウチをキャスティングすることによって、批判を受けながらも人種的な多様性をかろうじて担保しているといえる。それでも主役に白人俳優を配さざるを得なかった背景には、「アジア系の俳優では作品がヒットしない」という先入観から、映画業界ではまだ企画が通りにくい状況にあるからだろう。ただ、最近になって『ベイマックス』、『リメンバー・ミー』など、ディズニー、ピクサーの劇場長編・短編アニメ作品では、アジア系やヒスパニックのようなアメリカのマイノリティが主人公になるケースが増えてきているのも確かだ。
アダム・ウィンガード監督の才能
ゴジラとキングコングが戦う"Godzilla vs. Kong(原題)"にも抜擢されている、アメリカを代表する新時代の映像作家、アダム・ウィンガード。『ビューティフル・ダイ』、『サプライズ』など、前衛的なスリラー、ホラー映画でカルト的な人気を誇る映像作家で、とくに複数のジャンル映画を組み合わせた奇妙な、しかし新しい感覚を持った『ザ・ゲスト』によって急激に評価が高めた、実験的な作風の映画監督である。
映画作品としての評価
超大作モンスター映画を控え、娯楽要素が強い本作『Death Note/デスノート』は、その試金石とも考えられる一作ともなっている。ここで懸念されるのは、先進的な監督が趣味や実験に執心するあまり、娯楽作でありながら多くの観客が理解できないようなものになってしまうこと。または、分かりやすい作品を目指すあまり、個性を失ってしまうという結果だ。 しかし、本作はそのどちらにもならなかった。原作の娯楽性を踏襲しつつキャラクターに創意をくわえ、よりエモーショナルなものにしながら、地上波ではない配信作品だからこその残酷描写を連発することで、今までの『DEATH NOTE』実写作品では見られなかったインパクトのある表現が連発されている。 それはリュークの出現や“L”の育った施設のホラー表現、さらにFBIの捜査員たちがノートに操られ自殺するシーンなどにみてとれる。なかでもライトと“L”が夜のシアトルの裏道を延々と追いかけっこする、異様なユーモアを感じる展開は、今までのウィンガード監督のスリラー/ホラー表現や、ジャンルを逸脱していく実験的な特色をしっかりと打ち出しているのである。
バック・トゥ・80s(エイティーズ)
また、ウィンガード作品の多くに通底しているのが、80年代文化への回帰である。ニコラス・ウィンディング・レフン監督の『ドライヴ』、『ネオン・デーモン』にも見られるような、 ネオンカラーのような印象的な色の照明や音楽などの80年代ポップな感覚を、本作でもフェティッシュに再現した。 そこにあるのは、まず表面的な新しさを追い求めるような、チープさを持ったポップカルチャーの様式である。 『ザ・ゲスト』では80年代ヨーロッパのロックや エレクトロニック・ミュージックを中心に選曲されてたが、本作では一部を除いて、 INXS(インエクセス)やオーストラリアン・クロールなど、多くがオーストラリアの80年代音楽に統一され、指向性を強めている。本作ではそこから、現代では失われた当時の熱気や狂気を取り出し、本作における青春描写と重ね合わせているのだ。
アメリカにおける青春時代の殺人衝動とは
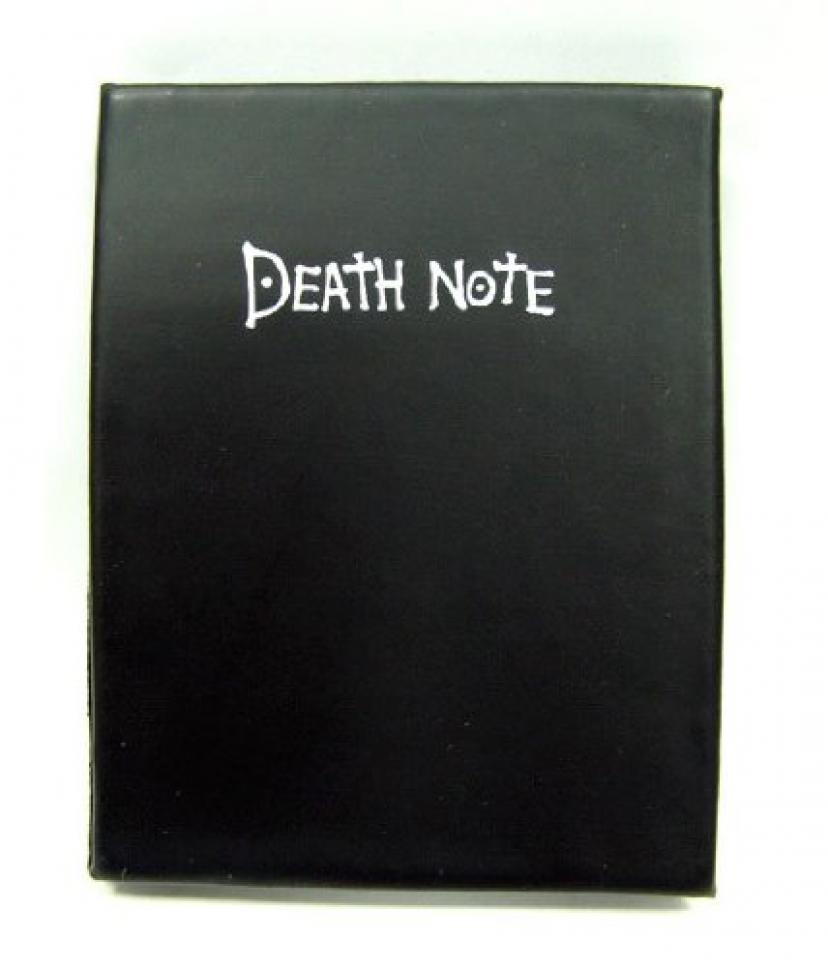
ウィンガード版での“デスノート”というアイテムは、学生時代の閉じられた環境からくる閉塞感のなかでの、いびつな願望や妄想の象徴ともなっている。 作品がそういった性質を帯びていくというのは、99年にアメリカで起こった、「コロンバイン高校銃乱射事件」が多くのアメリカ人の意識下にあるためだろう。いじめの被害に遭っていた男子高校生二人が学校内で発砲し、多くの死傷者を出したあの凄惨な事件である。
コロンバイン高校銃乱射事件
マイケル・ムーア監督のドキュメンタリー『ボウリング・フォー・コロンバイン』には、アニメ『サウスパーク』の製作者で、コロンバイン高校の卒業生でもあるマット・ストーンが出演し、事件時に自殺した犯人たちについてコメントしている。 「彼らは、自分たちを一生負け犬のままだと思っていたのかもしれない。もう少し我慢して卒業すれば、あとは自由なんだと誰かが彼らに教えてやれば良かった。」
アメリカの高校は隔絶された階層社会
乱射事件の犯人たちは、地元や学校、そしてスポーツマンやチアガールたち人気者が支配する、偏った価値観が支配する環境が世界の全てであると考え、目の前の絶望から抜け出すための手っ取り早い解決法として、殺人を選んでしまったのかもしれない。 本作は、そのオープニングシーンで示していたように、高校という閉鎖された特殊な環境に焦点を当てて、そのなかで抑圧を受ける一人の学生の殺人衝動を具現化したような“デスノート”というアイテムを通し、アメリカ社会のひとつの姿を見事に切り取ったといえるだろう。
漫画実写化作品を作る意義
小説と違って、もともと漫画にはヴィジュアルが備わっている。だから優れた原作のヴィジュアルやストーリーを、そのまま上手く(無難に)映像で再現した実写化作品というのは、意義の薄いもののように思える。そんな作品を鑑賞することは、原作を繰り返し読む行為とさして変わらないからだ。 その意味において本作『Death Note/デスノート』は、どの実写化作品よりも、作品の要素を新しいものとして提出できているように感じられる。漫画実写化作品というのは、こういうものであって欲しいと思う。
執筆者:小野寺系

![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)


















