【ネタバレ解説】戦闘のない戦争映画『戦場のメリークリスマス』はなぜ名作なのか

映画『戦場のメリークリスマス』はなぜ名作と呼ばれるのか
1983年に公開され、世界中で高く評価された名作『戦場のメリークリスマス』。戦時下の日本軍の軍人たちと、その捕虜となった外国の軍人たちとの邂逅を描いた本作は、戦争映画なのにも関わらず戦闘を描いていない点と、その情景の美しさに注目が集まった作品です。 また、特に有名なのが坂本龍一による音楽。エンディングで使用された「Merry Christmas Mr. Lawrence」は坂本の作品の中でも特に愛されており、多くのアーティストにカバーされるなど、広く知られている名曲です。 しかし古い映画ということもあり、本作のストーリーや名作と呼ばれる理由についてはあまり知られていないのではないでしょうか。今回は、本作のあらすじや制作の背景、大きな話題を呼んだキャスティングについて解説し、本作がなぜ名作と呼ばれているのかを考察します。 (※作中では捕虜を「俘虜(ふりょ)」と呼称していますが、この記事では同義の「捕虜」と表記します。)
舞台は戦時中のジャワ。2人の日本兵と2人の捕虜との邂逅を描く

舞台は戦時中のジャワ。日本軍統治下であったジャワには、日本軍捕虜収容所が置かれていました。 収容所内の事件をきっかけに、イギリス人捕虜ロレンス(トム・コンティ)と彼と共に事件処理にあたる日本人軍曹ハラ(ビートたけし)、イギリス人捕虜セリアズ(デヴィッド・ボウイ)と収容所の所長である陸軍大尉ヨノイ(坂本龍一)、という2組の邂逅を描きます。
イギリス人作家が戦争体験をもとに書いた小説「影の獄にて」が原作
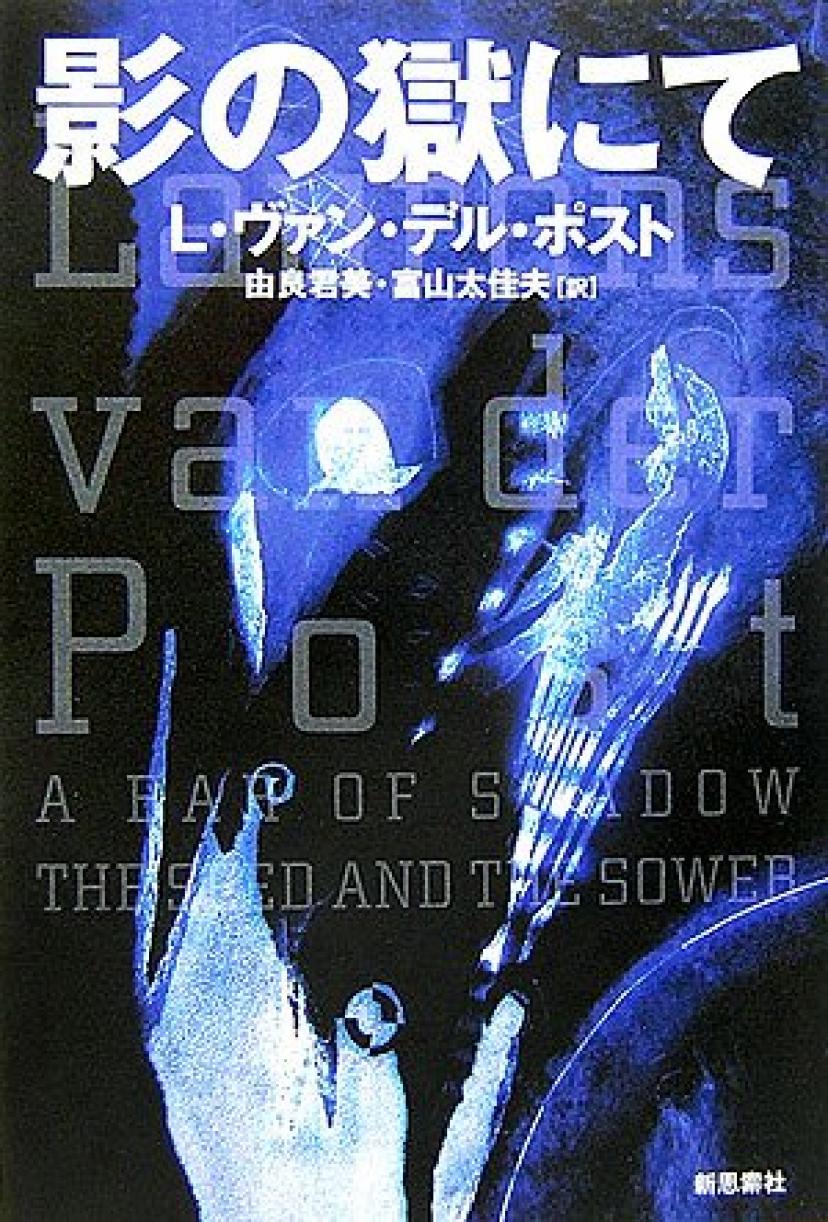
この『戦場のメリークリスマス』には原作となった小説があります。それは、イギリスの作家であるローレンス・ヴァン・デル・ポストによる「影の獄にて」。これは作者自身の戦争体験をもとに作られた作品です。本作に登場するロレンスとは、原作者自身を投影したキャラクターだったのですね。 映画版には語り手(ナレーション)が存在せず、ジャワでのロレンスたちの姿が直接描写されていくのに対し、この小説は語り手の「わたし」とロレンスがジャワでのことを思い出し語り合うという構成になっています。しかしどちらにおいても、収容所での2組の邂逅に焦点が当てられており、ストーリーはほとんど同じものとなっています。 小説でもロレンスとハラ軍曹の友情が中心に描かれており、またヨノイ大尉とセリアズ(小説ではセリエ)との交流も細やかに書かれています。 大島監督が本作だけでなく、生涯に渡って撮りつづけた「極限状態での人と人とのつながり」というテーマに合致した原作小説だったのです。
異色のキャスト!そのキャスティングの経緯とは
本作は登場人物が全員男性ということでもよく知られており、さらに、そのキャスト陣が俳優を本職としない様々な分野での著名人なのも、本作が異色作と呼ばれる大きな特徴です。 大島監督はしばしば俳優でないキャストを起用しましたが、その中でも特にその面が際立つ本作のキャスティング事情について紹介します。
厳格な軍人ヨノイを演じるのは日本を代表する音楽家・坂本龍一

本作の舞台となる収容所の所長・ヨノイ大尉は、規律に厳しいエリート武官です。厳格な雰囲気を持ち、2.26事件で“死に損なった”自身を恥じながら生きるヨノイを、YMOの坂本龍一が演じました。 この役は当初、高倉健や沢田研二などが打診されていましたが誰も折り合いがつかず、映画初出演にも関わらず坂本が抜擢されたのです。
世界的なアーティスト、デヴィッド・ボウイも出演

そんなヨノイ大尉はある日、収容された美しい捕虜ジャック・セリアズに惹かれていきます。そのセリアズを演じたのは有名なミュージシャン、デヴィッド・ボウイでした。 当初打診されていたのは名優ロバート・レッドフォードでしたが、アメリカ人の彼はこの作品が理解できないと辞退してしまいます。そんな時に、ブロードウェイミュージカルの『エレファント・マン』に出演するボウイを見て感動した大島は、自らボウイにオファーしたそうです。 脚本を読んですぐに出演を決めたボウイは「いつでもこの映画のためにスケジュールを空けるよ」と言い、それからクランクインまでの2年近く、本当にスケジュールを空けて映画の撮影に備えていました。
最後に大抜擢されたのは人気芸人・ビートたけし
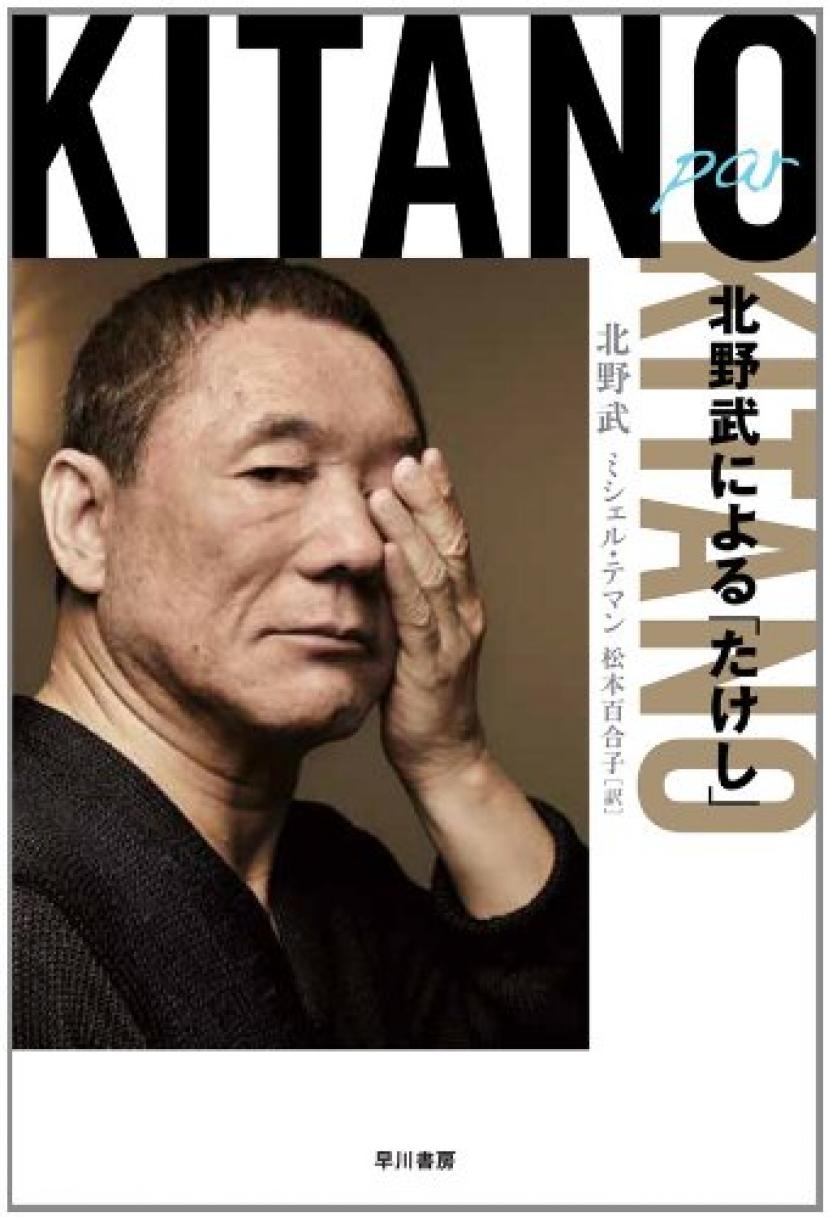
そして、最後にキャスティングされたのが、人気お笑い芸人のビートたけし。ヨノイの部下である粗暴な軍曹・ハラを演じました。当初ハラ役には勝新太郎や緒形拳の名前が挙がっていましたが、2人とも折り合いがつかなかったために、俳優経験の少ないたけしが大抜擢されたのです。 当時のたけしは「オレたちひょうきん族」でお笑い芸人としては人気の絶頂にあり、そんな彼の起用に一部のスタッフは反対したそうです。しかし、彼とテレビで共演したことのある大島渚監督は「瞳だけは美しく輝いている(ハラ役には彼がぴったりだ)」と反対を押し切り、大抜擢に踏み切りました。
職業俳優をメインに据えなかったことで生まれた、独特の味わいが凄い映画
最後に、ロレンス役を務めたのは、当時イギリスで人気を博していた俳優のトム・コンティ。彼は本作と同年に公開された映画『Reuben, Reuben』で主演を務め、アカデミー主演男優賞にノミネートされるなど、知名度は劣りますが実力のある俳優でした。 また、セリアズ役のボウイはミュージシャンとしての活躍が広く知られていますが、その一方で俳優として舞台や映画に出演していました。 それに対して、残りのメインキャストであるたけしと坂本は映画出演の経験がほとんどありませんでした。特に最後にキャスティングされたたけしに対して、スタッフからは「大丈夫か?」という声が出るなど、本人も大島監督の前で「オレは演技はできないよ」と不安の声を漏らしたりしていたそうです。 しかし、そんな2人が出演したからこそ本作は独特の雰囲気を持った名作たりえたのではないでしょうか。今もなおそれぞれの分野で世界的に活躍している2人ですが、本作は彼らにとって、その後のキャリアに大きな影響を与えたマイルストーン的作品とも言えそうです。 俳優としては素人だった彼らと本作との出会いが生み出したものは何だったのか、解説していきます。
ビートたけし演じるハラの持つ二面性
当時お笑い界のスターであったたけしは、俳優としてはほぼ素人でした。しかし彼はハラを演じるにあたり髪を剃って気合十分で撮影に臨み、味のある見事な演技を披露しました。 ハラは荒っぽい性格でしたが、聡明で日本語の話せるロレンスとともに収容所での事件の処理にあたったことで二人は友情を築きます。そしてハラは、無線機を持っていた疑いで処刑されそうになったロレンスとセリアズを釈放するという優しさも見せたのでした。 また、ハラは国に忠実な帝国軍人である半面、聡明な面も持った人物でした。「捕虜になり恥をかくくらいなら自決するべきではないか?」という彼の問いかけに「捕虜になるのは恥ではない」と答えるロレンスを「理解できない」とは言いつつも、その西洋的な価値観を否定することはなかったのです。 キャスティングの段階で大島監督はハラ役にはたけしがぴったりだと考えていましたが、荒々しい性格でありながらも聡明で美しく輝く瞳を持つ、というハラのイメージは、確かに若かりし頃のたけしによく合っています。
本作の代名詞のラストシーンにおける名演
そんなハラでしたが、戦争が終わると敗戦国の軍人という立場に立たされて投獄されてしまいます。自由の身となったロレンスは旧友として彼のもとを訪れ、昔のことを語り合いました。かつてとは逆の立場でロレンスを迎えたハラの、恥ずかしがりながらも嬉しそうな表情は彼の性格をよく表しています。 しかし、それ以上にたけしの名演が見られるのはラストカットです。別れ際にハラは「メリークリスマス、ミスターロレンス!」と叫び、ロレンスを見送ります。自らの運命を覚悟したハラは清々しい笑顔を浮かべていましたが、その目は涙で潤んでおり、どこか切なさを感じさせる表情でした。 このカットで物語は終わり、坂本による有名な主題歌とともにエンドロールが流れます。公開当初は、このエンドロールの間、感動した観客たちによる拍手が鳴りやまなかったそうです。
本作がきっかけでたけしは「世界のキタノ」に
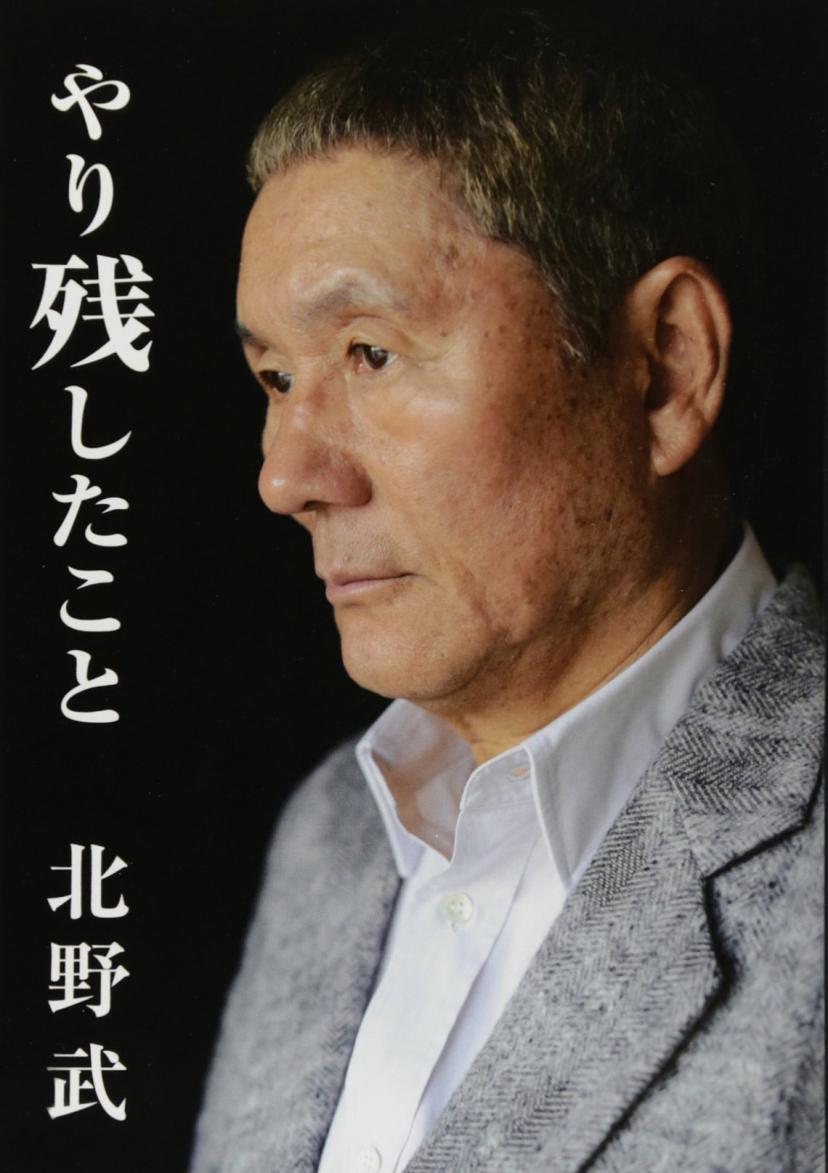
たけしは本作の完成後に自分の演技が下手だと落ち込んだそうですが、大島監督は彼の演技を絶賛し、共演していた俳優のジョニー大倉や内田裕也はたけしの存在感の大きさに嫉妬したといいます。 本作をきっかけにたけしは映画界で活躍し始め、今では「世界のキタノ」と呼ばれるまでになりました。そんなビートたけしは、大島監督が亡くなった時に本作を振り返り「龍一さんが海外で賞をとって、私も映画で賞をとってね。きっかけは、その辺だったと思う。ありがたい」と語っています。
坂本の雰囲気や佇まいがぴったりだったヨノイ大尉

たけし以上に俳優としては素人だったのが、本作で映画初出演を果たしたヨノイ役の坂本です。彼は台本を全く覚えずに現場入りしましたが、厳しいことで有名な大島監督はなぜか坂本の代わりに相手役の俳優を叱責したそうです。そんな大島監督の配慮もあり、坂本は無事クランクアップを迎えました。 本作での坂本の演技には賛否両論あります。公開当初酷評されていたように「セリフが棒読みすぎる」という意見がある一方で、「表情の演技が良い」という意見も多く見られるのです。 彼が演じたヨノイ大尉は、その厳格な佇まいと「死に損ない」である自身を否定するような雰囲気が特徴的な人物です。坂本は演技力よりも、彼自身がもともと持ち合わせている雰囲気や存在感でヨノイ役を見事に演じました。
ヨノイ大尉のセリアズへの想い

ヨノイはセリアズの裁判に立ち会った時から彼に惹かれていたように見えます。冒頭でオランダ人捕虜のデ・ヨンを強姦した軍人のカネモトが処刑されたことからわかるように、当時同性間の性愛は悪とされていました。規律に厳しく、実直な彼が同性に恋をしているなど、彼自身が自覚できるわけがなかったのです。 しかし、反抗的な捕虜に腹を立て処刑しようとしたヨノイにセリアズがキスをしたことで、ヨノイは自分の想いに気付いてしまいます。ショックのあまりヨノイはその場で膝から崩れ落ち、所長の職から退いてしまうのです。 この場面での坂本の演技は素晴らしいものでした。セリアズからの突然のキスに対する戸惑いと、今まで目を背けていた自分の恋心を自覚してしまったことへのショックがその表情からよく感じ取れます。 また、このシーンではカメラが微妙に動いているのですが、実はこれは演出ではなくトラブルだったそうです。しかし大島監督はこのぶれによってヨノイの心情がより強調されていると、このカットを使用したのでした。
坂本龍一による有名すぎる楽曲

本作の主題歌は、ヨノイ大尉役として出演している坂本龍一によるものです。当時YMOのメンバーとして活躍していた坂本は、大島監督から出演のオファーがあった際に「音楽も自分にやらせてください」と頼んだといいます。現在では映画音楽家としても知られる坂本ですが、本作で初めて映画音楽を手がけたのです。 彼は撮影中に一度だけカメラをのぞいていた時、音楽が聞こえてきたと語ります。その体験をもとに、200時間以上もスタジオにこもって生まれたのが、本作の感動的なサウンドトラックです。中でも有名な「Merry Christmas Mr. Lawrence」の美しくどこか切ない旋律は、誰もが聴いたことがあるでしょう。
その後、坂本は『ラストエンペラー』の音楽を担当したことで、日本人として初めてアカデミー作曲賞やグラミー賞を受賞し、世界的な映画音楽家となりました。 ちなみに、この「Merry Christmas Mr. Lawrence」が自身の楽曲の中でも屈指の人気曲となっていることについて、本人は「よくわからないが、メロディが覚えやすいからではないか」とコメントしています。
“戦闘が描かれない”ことの意味は何だったのか?

本作は戦時下の兵士たちの姿を描いた戦争映画ではありますが、他の戦争映画と大きく異なるのが、戦闘シーンが一切ない点です。これにはどんな意味があるのでしょうか?
ハラとロレンスの友情から考える
日本の軍人であるハラとイギリス人捕虜であるロレンスとは心を通わせていきますが、やはり2人の間には大きな価値観の違いがありました。捕虜になることへの考え方の違いを2人が語るシーンでそれは顕著に表れています。 そしてラストシーンでは、ロレンスがハラに「あなたは自分こそが正しいと信じ込んでいた、過去のあなたの犠牲者だ」と語りかけます。ロレンスはハラをはじめとした日本軍の価値観をおかしいと思いながらも、ハラに対しては友好的でした。 最後に「メリークリスマス」といってロレンスを見送るハラですが、作品中盤、酔ったハラがロレンスとセリアズを釈放するシーンにも同じセリフがあります。この最後のセリフについては様々な考察がありますが、ハラの「あの時から変わらず自分たちは友だちだ」という気持ちを込めてのセリフと考えられます。
戦闘を描かないことで伝えたかったテーマは?
これらを通じて考えてみると、「お互いの価値観の相違について理解することで、価値観の隔たりはを越えたつながりを持つことができる」というテーマ性を感じ取ることができます。そしてそこには、戦争の無意味さや虚しさというテーマも含まれているのではないでしょうか? 本作は、戦闘を描かなくとも戦時下における対立する立場の人間の相克を描くことはできる、ということを私たちに伝えます。それはつまり、戦争における戦闘=殺し合いは無意味だということの暗喩のように私は考えました。
『戦場のメリークリスマス』はいつまでも示唆に富んだ名作であり続ける

本作は戦争映画でありながら戦闘を一切描かず、男性同士の性愛を高雅なものに昇華して描いた異色の作品で、それらがキャストたちによる味のある演技や坂本による抒情的な音楽によって美しく彩られています。 今回は本作のストーリーやキャストの紹介、また名作とされている理由について考察しましたが、本作が長年にわたり名作として愛されているのはその耽美的な雰囲気だけでなく、奥深いテーマ性に依るものでもありました。 そんな本作ですが、公開から30年以上が経った2019年現在においては、公開当初とはまた違う意味をもった作品となっている、ともいえそうです。現在は戦争の記憶も日本社会にはほぼ残っておらず、また男性同士の性愛に対する価値観も公開当初から大きく変わっているからです。 そんな現在では、本作はその音楽や演出の美しさがより大きくフォーカスされ、ますます愛される映画となりました。しかし、今もなお戦争の足音は鳴り止まず、人間の価値観の対立は起こり続けています。 当時の背景などを考えながら本作をもう一度観てみると、新たな発見があるかもしれませんね。
![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)



















