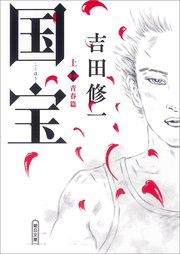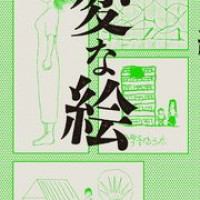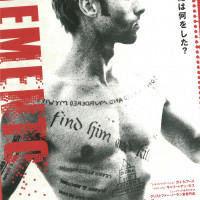映画『国宝』徳次は生きている?原作から描かれなかったその後の人生を紐解く

前代未聞の異例の大ヒットを続けている映画『国宝』。原作は吉田修一による同名の芸道小説で歌舞伎界がメインの舞台ですが、主人公・喜久雄の生い立ちから極道の世界も描かれています。 この記事では、喜久雄の兄貴分である徳次について、映画と小説の両方からその人生に迫っていきます。 映画『国宝』の重要なネタバレを含みます。未鑑賞の方はご注意ください。
『国宝』早川徳次のプロフィール
| 名前 | 早川徳次(はやかわとくじ) |
|---|---|
| 年齢 | 16歳(喜久雄の2歳上) ※初登場当時 |
| 出身 | 長崎 |
長崎の名門侠客一家・立花組の部屋住み込み組員だった早川徳次。立花組は喜久雄の父親・立花権五郎が組長であり、徳次は喜久雄を「坊ちゃん」、喜久雄は徳次を「徳ちゃん」と呼んで兄弟のように育ちました。 ここからは映画・小説両方から、徳次の活躍を振り返っていきます。
映画『国宝』における徳次の登場シーンをおさらい
宴席での「関の扉」喜久雄の相手役を担う徳次
映画では冒頭の立花組の新年会で、歌舞伎の演目「関の扉」を喜久雄と一緒に演じた徳次。そこには花井半二郎も見に来ていましたが、宮地組の殴り込みに遭ってしまいます。父を目の前で殺されて憤る喜久雄を半二郎が抑えていました。
喜久雄と共に仇討ちへ
父を殺された喜久雄は徳次と2人で敵討ちに向かいました。しかし幼なじみの春江には止められ、結局は敵討ちは失敗したことがうかがえます。実は小説では喜久雄が1人で中学校の朝礼で宮地組の親分を刺すという敵討ちを行い、それが原因で大阪へ出されるという展開。 小説では徳次も一緒に大阪へ向かいますが、映画では敵討ちのシーンを最後に登場していません。
徳次は死亡していない?映画と原作小説の違いを解説!
映画では敵討ちの後、徳次がどうなったのかには言及されておらず、「もしかして死んだ……?」と思っている人も多いよう。しかし小説では前述の通り、徳次とともに大阪へ行き、一緒に半二郎の世話になっています。 その後も徳次の人生は波乱万丈で、それでも近くでも遠くからでも常に喜久雄の活躍を見守り続けていたのです。
実は映画の中にも徳次の影が⋯⋯
登場は長崎のシーンのみだった徳次ですが、実はその後も徳次の存在が演出されていました。喜久雄の楽屋に贈られてくる花輪が春江と徳次からであることが確認できます。しかも落ちぶれて花輪も少なくなり、ついに春江からも送られてこなくなっても、徳次だけは花輪を送り続けていました。 劇中最後に国宝となった喜久雄が「鷺娘」を演じた楽屋にも、徳次から贈られた暖簾がかかっていました。
小説での徳次は重要なキーパーソン
実際のところ、小説での徳次は「影の主役」だとすら評する人もいる模様。それぐらい重要な役どころであり、徳次は常に喜久雄を見守り、深くつながっていました。 小説は上下巻合わせて800ページを超える大作であるため、それを3時間の映画に収めるためには多くのエピソードを削らなければならなかったのでしょう。
ネタバレあり!映画では描かれなかった徳次のその後の人生を解説

ここからは小説での徳次の活躍を、彼の人生を追ってまとめていきましょう。小説のネタバレが含まれていますので、先に読むことをお勧めします。
長崎の立花組で喜久雄の兄貴分に

戦後の長崎で、一大侠客一家となっていた立花組。大阪の丹波屋にもその名が知られるほどの大組織であり、上方歌舞伎の人気役者・花井半二郎が挨拶に立ち寄るくらいの名門だったことがうかがえます。 そんな立花組に拾われ、舎弟として部屋住み込みの組員となった徳次。喜久雄とともに難しい歌舞伎の演目を演じたり、敵討ちをひたすら心配したりと度胸と優しさと情に溢れた人物として描かれています。
喜久雄の家族を支える情の厚さ

喜久雄の愛人である藤駒とその娘・綾乃を、実は影から支えていたのも徳次でした。喜久雄との関係を悪化させないよう尽力していたのです。 例えば綾乃の誕生日を忘れていた喜久雄の代わりにプレゼントを用意したり、藤駒(小説では市駒)に「明日一緒に居られない」と電話しておくように促したり。綾乃の成長を影から見守っていました。
綾乃を守るために筋を通す任侠の漢
徳次は綾乃を溺愛していましたが、その愛情深さは成長した綾乃がグレて不良とつるんで危険な目に遭った時にも発揮されます。不良の家でシンナーを吸ってヤクザ絡みのトラブルに巻き込まれた際、組長と相対しても一歩も引かず、しっかり筋を通して小指を詰めて事を収めたのです。 徳次の肝の据わり方と情の厚さがよくわかるエピソードではないでしょうか。
中国に渡り一大企業の社長に
徳次は大阪から北海道に渡って事業を始めたり、最終的には中国大陸に渡って「白河公司」という企業を立ち上げて社長になっています。そして援助できるほどの財力を蓄えて遠くの地から喜久雄を見守り続け、綾乃たちを支えていたのです。 喜久雄の「鷺娘」の公演チケットを綾乃に送ってきたのも、実は徳次だったということがほのめかされていました。
実はあのセリフは徳次のものだった!?
徳次は映画では序盤にしか登場しませんが、小説では影の主役といわれるほど大きな役割を担っており、心に残るセリフもたくさんあります。実は映画では徳次のセリフは別の登場人物に託されており、しかも重要な場面に使われているのです。
娘・綾乃「芝居見るとな、正月迎えたような気分になんねん。」
このセリフは映画では終盤近く、綾乃が国宝となった父・喜久雄を取材する場面で言っていました。小説ではやはり終盤近くの「鷺娘」公演の日、中国から駆け付けた徳次が車内で秘書にこう語っています。 「その役者の芝居みるとな、正月迎えたような気分になんねん。気持ちがキリッとしてな。これからなんかええこと起こりそうな、そんな気分にさせてくれんねん。そんな役者、ほかにおるか?」 映画では綾乃が不義理だった父に対して恨み節半分、しかし才能を認めざるを得ない気持ち半分で実に微妙な心境を表すのに使われていました。とても印象的なシーンだったため、覚えている人も多いのではないでしょうか?
ライバル・俊介「お前ほんまに彰子ちゃん騙したんか。」
喜久雄が彰子の家柄を利用したことを詰ったのは、映画では俊介でしたが、小説では徳次でした。このセリフは映画オリジナルのようで、小説では徳次はこう言っています。 「見損のうたわ!俺が知ってる坊ちゃんはな、そんな男やないわい!」 またそれを受けた喜久雄が彰子に本当のことを告白すると、彰子は「中途半端なことしないでよ!騙すんだったら、最後の最後まで騙してよ!」と、すべて承知の上だったことがわかり、映画のキャラクターより芯の強さを感じさせます。
幼馴染・春江「楽屋にペルシャ絨毯買うたる。」
喜久雄のプロポーズを断った際、働いて喜久雄を支えようとする意志の強さを表すために、映画では春江がこのセリフを言っています。小説では徳次が喜久雄から離れて、大阪から北海道へ渡って事業を起こそうとする時にこう語っていました。 「将来事業起こして成功した暁には、誰よりも立派な坊ちゃんのご贔屓さんになって、楽屋にペルシャ絨毯買うたるし、もっと成功したら専用の劇場も作ったるから、それまで坊ちゃんは、地道に芸道に励んどいてえな」 徳次は有言実行の男で、中国に渡って20年、大企業の社長になってその夢を叶えています。
『国宝』徳次を演じたキャストは下川恭平
早川徳次を演じたのは、2004年8月11日生まれ、北海道出身の俳優・下川恭平です。子役から活躍しており、2022年の舞台「『鬼滅の刃』其ノ参 無限夢列車」で炎柱・煉獄千寿郎役を務めています。 呉美保監督の『きみはいい子』(2015年)に出演し、その縁で吉沢亮主演の『ぼくが生きてる、ふたつの世界』の主題歌を担当。2025年4月19日にはファーストシングル「紡ぐ春」をリリースしています。
徳次は一生を懸けて坊ちゃんを見守った
小説では物語の重要なセリフを担い、ずっと喜久雄を見守り続けた唯一の人物で、その存在感が誰よりも強かった早川徳次。映画では時間の都合上、徳次の活躍が見れなかったのは残念ですが、この機会にぜひ原作小説を読んでみてください!
![ciatr[シアター]](https://ciatr.jp/images/header_logo.png)